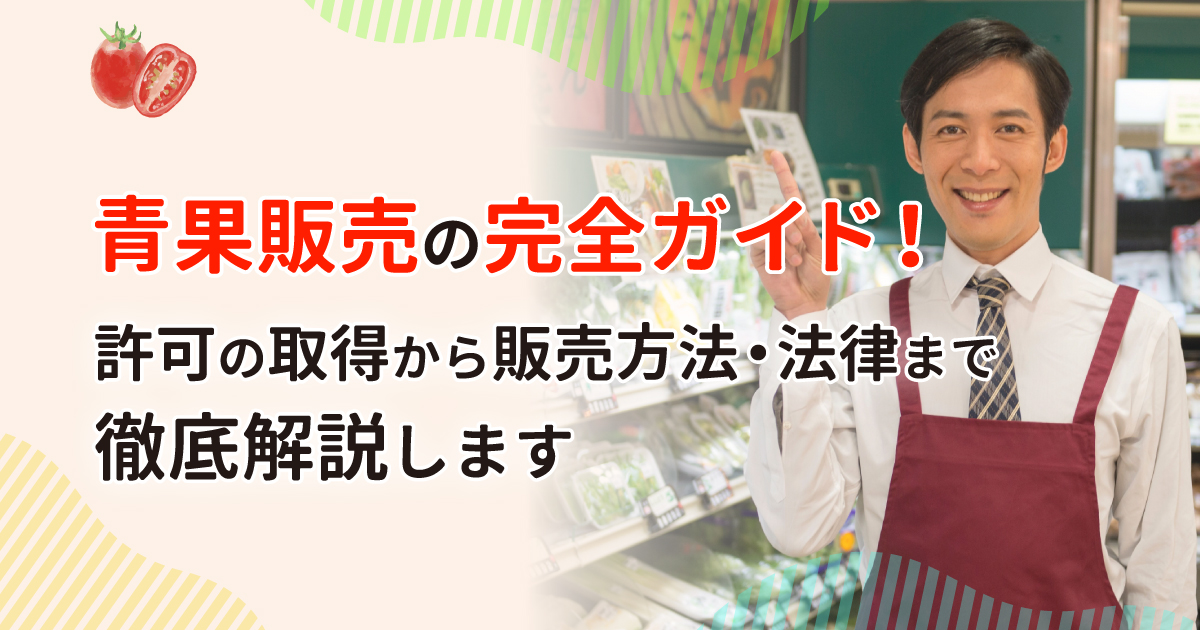「家庭菜園で採れた野菜を販売してみたい」
「ネットショップで果物を売ってみたい」
── そう思ったことはありませんか?
身近に感じる一方で、いざ始めようとすると意外と知らないことが多いのが野菜や果物の販売です。
近年では、個人でも気軽に青果の販売を始められる環境が整いつつありますが、実は販売方法によっては必要な許可や手続きが異なるため、事前の確認が欠かせません。
「知らずに始めてしまったら違法だった…」というケースも少なくないのです。
この記事では、青果販売に必要な準備や手続き、食品表示や衛生管理のポイント、さらに売上アップのヒントまで、初心者にもわかりやすくまとめました。安心して第一歩を踏み出すために、ぜひ最後までご覧ください。
青果の販売に許可は必要? ルールと法律を解説
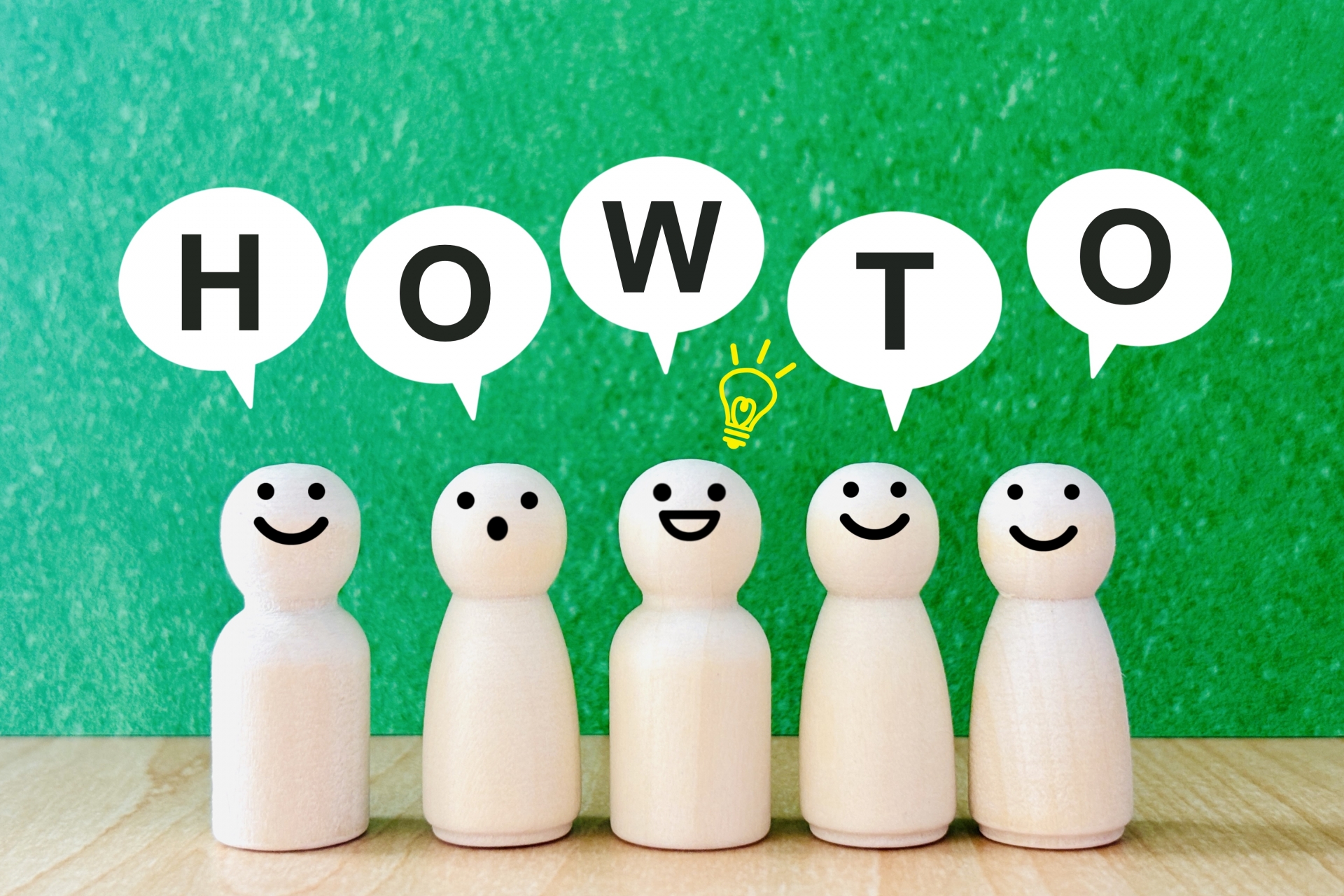
青果販売を始めるうえで、まず確認すべきなのが「販売に許可が必要かどうか」という点です。実は、青果の販売方法によって、必要な許可や届け出が大きく変わります。
まずは、① 自家栽培の青果を販売するケース、② 他人から仕入れて販売するケース、そして③ 加工して販売するケースに分けて、基本的なルールと関係する法律を見てみましょう。
① 自家栽培の青果を販売するには? 許可不要でもルールあり
自分で栽培した未加工の青果を販売する場合、原則として保健所の営業許可は必要ありません。これは、農産物が「食品衛生法」の適用外となるためです。
そのため、自分の畑で育てた野菜や果物を直売所や無人販売所で販売することは、比較的ハードルが低いといえるでしょう。
ただし、許可が不要であっても「何をしても自由」というわけではありません。
販売する青果には、食品表示法に基づいた表示(産地・品種・販売者名など)が必要で、衛生的な環境での保管や陳列、害虫対策なども重視されます。
とくに、不特定多数に販売する場合は、トラブルを避けるためにも基本的なルールを押さえておくことが大切です。
② 購入した青果を販売するには? 仕入れ販売の許可が必須
他の農家や業者から青果を仕入れて販売する場合には、「野菜果物販売業」として保健所への営業届出が必要になります。
この届出は、食品衛生法の一部対象業種として分類されているためで、販売所の所在地や販売スタイル(店舗・移動販売・ネットなど)に応じた対応が求められます。
● 届出は「販売を始める10日前まで」に販売場所を管轄する保健所に提出しましょう。
対象となるのは、実店舗での販売だけでなく、移動販売車やネットショップ(自社EC、メルカリなど)での販売も含まれます。
届出にあたっては、販売施設の所在地・代表者・取扱品目などを記載し、書面または電子申請で行います。
※「菓子類」や「漬物」などの加工品を一緒に扱う場合は、別途許可が必要になる場合があります。
📎 出典:厚生労働省「新たな営業届出制度について」
また、仕入れ販売を行う場合は、販売する青果の状態や品質管理の方法にも責任が伴います。
販売業者として、信頼できる仕入れ先を選ぶことや、商品の保管・陳列方法にも注意を払いましょう。
③ 青果を加工して販売するには? 必要な設備と手続き
青果をカットしたり、漬物やジュースに加工して販売する場合は、保健所の営業許可が必要となります。
これは「食品製造業」「そうざい製造業」といった業種に該当するためで、調理や加工を行う施設が一定の衛生基準を満たしているかどうか、が審査の対象となります。
施設基準には、手洗い設備や作業場の動線、冷蔵・冷凍設備の整備などが含まれ、営業開始前に図面の提出や現地調査が行われることもあります。
とくに、加熱処理を行わない生鮮加工品は衛生リスクが高いため、細かい管理が必要です。
【食品表示法と食品衛生法の基礎知識】販売前に知っておくべき法律とは?

青果販売を始める際には、食品表示や衛生管理など、いくつかの法律を守る必要があります。とくに関わりが深いのが、「食品表示法」と「食品衛生法」です。
これらは、消費者が安全・安心に食品を購入できるよう定められた法律であり、青果を扱ううえでも基本となる知識です。
ここからは、それぞれの法律が求めるルールと、実際に販売を行う際の注意点について見てみましょう。
食品表示は正しく記載! 「原材料・産地・賞味期限」のルール
青果の販売において、食品表示法に基づいた表示は欠かせません。生鮮食品の場合は、主に「品名」「産地」「販売者名」の3つが基本表示項目となります。
とくに、道の駅や直売所、ネット販売では、誰が・どこで作った青果かを明確に伝えることが信頼性につながります。表示ラベルやPOPなどを活用して、見やすく・わかりやすく伝える工夫をしておきましょう。
一方、加工品になると、表示項目はさらに増え、「原材料名」「内容量」「消費(賞味)期限」「保存方法」「アレルゲン表示」などが必要になります。
たとえば、カット野菜やジャム、漬物などを販売する際には、これらの情報をラベルやパッケージに正しく記載する義務があります。
表示に不備があると、行政指導や商品の販売停止といったリスクが生じるため、事前に保健所や行政のガイドラインを確認しておきましょう。
また、インターネット販売では、商品ページにも同様の情報を掲載する必要があります。
事前にチェックリストを作成し、漏れがないか定期的に確認できるようにしておくとよいでしょう。
衛生管理は基準を徹底! 手洗い設備や冷蔵保管のポイント
食品衛生法では、青果の取り扱いや保管に関しても一定の基準が設けられています。
たとえば自家栽培品であっても、多くの人に販売する場合は、施設の清潔さや衛生的な取り扱いが求められるため、しっかり意識しておきたいポイントです。
とくに重視したいのが、販売所や加工施設では手洗い設備の設置や、作業環境の清潔さ。従業員のこまめな手洗いや器具の洗浄・消毒を習慣づけることは、異物混入や細菌の繁殖を防ぐことに直結します。
販売前にチェックリストを用意し、毎日の清掃・衛生管理をルーティン化しておくと安心でしょう。
また、青果は品目によって適切な保存温度が異なるため、冷蔵設備や温度計の設置などを通じて、鮮度を保つ管理体制を整えることも欠かせません。
中でも、カットフルーツやサラダなどの生鮮加工品は、温度管理の不備が変質による返品対応や、食中毒のような事故といったトラブルの原因となることも。
取り扱う商品の特性に応じて、必要な設備や温度管理体制をあらかじめ確認・整備しておきましょう。
このように、販売所の規模にかかわらず、日常的な清掃・消毒・点検の習慣化が、安全な青果販売を支える基盤となります。
【販売先・販売方法別】許可や届け出のルールをご紹介

青果の販売方法にはさまざまなスタイルがあり、どこで・誰に・どう売るかによって、必要な許可や手続きが大きく変わります。
最近では、道の駅や直売所などの地元密着型の販売に加え、インターネット販売やイベント出店、移動販売といった柔軟な方法も広がっており、販売形態ごとに対応すべきルールや準備内容も多様化しています。
それぞれの販売方法には、守るべきルールや準備すべき設備が異なるため、自分のビジネスに合った形式を選び、事前に必要な手続きを把握しておくことが大切です。
ここからは、代表的な販売方法6種類を挙げます。それぞれに必要な許可や届け出のポイントを整理していきましょう。
「農協や道の駅に出荷する場合」は、登録が必須! 販売基準も要確認
農協(JA)や道の駅に青果を出荷する場合は、あらかじめ生産者としての登録や契約が必要です。
とくに農協では、部会への加入や生産履歴の提出が求められることがあり、道の駅でも地域性や出品基準に基づいた審査や書類の提出が必要となるケースがあります。
どちらの施設でも形やサイズ、鮮度といった品質基準をクリアしなければ出荷できないため、収穫前から規格を意識した栽培管理をしていきましょう。
また、販売ルールや価格設定が施設側によって定められていることも多いため、トラブルを防ぐためにも事前の確認は欠かせません。
「直売所や無人販売を開設する場合」は、設備基準と衛生管理が重要!
自宅の敷地や畑のそばに直売所や無人販売所を設置する方法は、比較的手軽に始められる青果販売のスタイルです。
許可が不要なケースもありますが、地域によっては、販売所の屋根や棚の設置、簡易的な冷蔵機能、ポップや価格表示など、消費者が安心して購入できる環境づくりをルール化している自治体もあります。
見落としやすいポイントなので、開設前に自治体のガイドラインや保健所の指導内容を確認しておきましょう。
また、無人販売では盗難や商品の傷みといった品質管理のリスクも見逃せません。
防犯カメラの設置や、こまめな補充・清掃体制を整えておくことで、トラブルを未然に防ぎ、信頼感のある売り場づくりにつなげましょう。
「移動販売を行う場合」は、営業エリアと保健所の届出を確認!
軽トラやキッチンカーを使った移動販売は、販売場所を柔軟に選べる点が魅力ですが、多くの場合、各自治体での営業許可や届出が必要となるため注意が必要です。
とくに、移動するエリアが複数の市区町村にまたがる場合、それぞれの自治体でルールが異なることがあるため、事前に保健所へ確認しておきましょう。
さらに、「販売車両の設備」も重要なチェックポイント。野菜や果物の保管スペースはもちろん、衛生的に取り扱える環境が確保されているかどうかが、営業許可の審査対象になることもあります。
イベント出店を兼ねる場合は、主催者側の出店条件や衛生管理基準も事前に確認しておきましょう。
「マルシェやイベントに出店する場合」は、許可の有無と食品衛生法をチェック!
地域のマルシェやイベントでの出店は、集客力が高く、青果の魅力を直接伝えられるチャンス。試食や対面販売などで、商品の鮮度や生産者の想いを伝えられるのも大きなメリットでしょう。
ただし、イベントによっては出店者に営業許可を求めるケースもあるため、主催者や開催地の保健所に事前確認することが重要です。
また、販売環境によっては食品の状態が変化しやすく、衛生リスクが高まる点にも注意しましょう。
とくに、屋外では気温や衛生環境の管理が難しくなるため、テント設置や冷蔵設備の用意など環境対策が欠かせません。
生食用の青果やカット野菜を扱う場合は、食品衛生法に基づいた衛生管理体制をあらかじめ整えておきましょう。
屋外でカット青果を販売する際の
衛生管理ポイント
屋外でカット野菜やフルーツを扱う場合は、10℃以下で冷蔵保存できる体制を整えることが基本。販売中は直射日光を避けるテントの設置や、手洗い・消毒の備えも重要です。また、虫の侵入や異物混入を防ぐために、フタ付き容器や簡易シールドを活用しましょう。
「インターネットで販売する場合」は、食品表示と配送ルールがマスト!
ネットショップやフリマアプリを使ったオンライン販売は、遠方の消費者にも商品を届けられる利点があります。
ただし、実物を見られない販売方法だからこそ、正確な情報提供と配送品質の管理がとくに重要です。
商品ページには、食品表示法に基づく情報(品名・産地・販売者・保存方法・消費期限など)を正しく記載しましょう。
また、生鮮品を扱う場合は、クール便や保冷梱包などの適切な配送手段を選ぶことが信頼性のカギとなります。
到着時のトラブルを防ぐためにも、返品対応や問い合わせ先なども明確に表示しておきましょう。
「他店舗の直売所や店先で販売する場合」は、契約内容と手数料を確認!
スーパーや商業施設が運営する直売所、または他人の敷地に設けられた販売スペースを利用する場合は、委託販売形式となることが多いため、契約条件の確認が欠かせません。
出荷者としての登録や、売上に対する手数料の仕組み、返品ルール、在庫補充の責任分担などをしっかり把握しておきましょう。
また、売り場のスペースや清掃・衛生管理を販売者自身がどこまで担うのかも、施設側と取り決めておくとトラブル防止につながります。
信頼できる施設や担当者との関係づくりが、継続的な販売のポイントになりますので、事前にしっかりコミュニケーションをとっておくようにしましょう。
保健所や行政への手続き3ステップ! 許可取得の流れを解説します

青果販売を本格的に始めるには、保健所や行政への手続きが必要になるケースがあります。とくに「仕入れ販売」や「加工販売」を行う場合は、営業許可の取得が前提となるため、事前の準備と段取りが欠かせません。
許可申請には、施設の条件や衛生管理体制の確認、必要書類の提出など、いくつかのステップを踏む必要があるので、はじめて申請に取り組む方にとっては少しハードルが高く感じられるかもしれません。
ポイントを押さえればスムーズに進められるので、まずは、許可取得までの「申請 → 審査 → 維持・更新」の3ステップに分けて、手続きの流れを確認しましょう。
① 許可申請を行う! 必要な書類と準備のポイント
青果販売を始めるにあたって、まず必要になるのが営業許可の取得です。
とくに「仕入れ販売」「加工品の販売」などを行う場合は、保健所への申請は必須。扱う商品が「生鮮青果物」か「加工食品」かによって、必要な許可の種類や提出書類が異なるので、事前に自治体の保健所へ相談しておきましょう。
一般的には、施設の図面(平面図)、営業計画書、食品衛生責任者の資格証明書などが必要となります。施設の構造や衛生管理体制が審査対象になるため、開業前にしっかり整備しておくと安心です。
また、申請には行政手数料がかかる場合もあるため、あわせて確認しておきましょう。申請様式は多くの場合、自治体の公式サイトからダウンロード可能です。事前にチェックしておくと◎
② 審査をクリアする! 許可取得までのプロセスと流れ
申請書の提出後は、保健所による書類審査と現地調査(施設の衛生確認)が行われます。
調理スペース・手洗い設備・冷蔵保管設備などが、食品衛生法や各自治体の施設基準に適合しているかがチェックされます。
施設が完成していない段階で申請すると、追加工事や再検査が必要になることもあるため、設計段階から保健所に相談しておくのが安心です。
審査から営業許可証の交付までには、数日〜数週間程度かかるのが一般的です。
飲食イベントやマルシェ出店、オンラインショップのオープンなど予定がある場合は、営業許可の取得スケジュールを逆算して準備を進めるようにしましょう。
③ 許可を維持・更新する! 管理と手続きの進め方
無事に営業許可を取得しても、それで終わりではありません。許可には有効期限があり、一定年数ごとに更新手続きが必要になります(通常は5〜6年ごと)。
また、販売方法や設備に変更が生じた場合には、変更届の提出や再申請が必要になることも少なくありません。
たとえば、加工品の製造を新たに始める場合や、施設を増築するようなケースは要注意。
日常的に衛生管理の記録や点検、従業員への教育体制などを継続していくことが、トラブルを防ぐうえで大切なポイントとなります。
継続的な衛生管理や設備維持を通じて、営業許可の更新・継続に向けた信頼性の高い運営体制を整えていきましょう。
販売施設・設備で注意したい “衛生管理ポイント”

青果は生鮮食品であるため、販売する施設や設備の衛生管理が欠かせません。
せっかく良い商品を仕入れても、保管方法や清掃体制が不十分だと、品質の低下や食品トラブルにつながることも。衛生対策は「あとから整える」のではなく、販売開始前から計画的に整備しておきましょう。
また、保健所による立ち入り検査や営業許可の更新をスムーズに進めるためにも、日頃から衛生対策に取り組む姿勢が重要です。
衛生管理マニュアルの整備やチェックリストの活用など、日常的に取り組める体制づくりを進めておきましょう。
ここでは、青果の鮮度を保つための環境整備や、害虫を防ぐための対策、従業員教育まで、施設・設備に関する衛生管理のポイントをご紹介します。
「青果販売における保管の基本」温度・湿度の管理ポイント
青果は品目によって最適な保管条件が異なるため、適切な温度・湿度管理が欠かせません。
青果は品目によって最適な保管条件が異なりますので、「葉物野菜は低温・高湿度」、「根菜類はやや高めの温度」といったように、それぞれの特性を把握したうえで保管環境を整えましょう。
とくに、販売所や直売施設では、冷蔵ショーケースや保冷庫を導入するなど、温度・湿度の管理ができる設備の整備が求められます。
温度計や湿度計を活用して、日常的に数値を確認・記録しておくとトラブル防止に役立つでしょう。
さらに、保管場所の直射日光や熱源の影響を避ける工夫も必要です。とくに夏場は、商品の鮮度が落ちやすいため、保冷ボックスや断熱材なども上手に活用して品質を保ちましょう。
「害虫を防ぐ」定期的な清掃と衛生管理の重要性
青果は香りや水分によって虫を引き寄せやすいので、販売施設ではとくに害虫対策が重要です。
店内や販売スペースの隅にホコリや食品くずが残っていると、コバエやゴキブリなどが発生しやすくなりますので、気をつけましょう。
害虫の発生は、清掃不足や食品カスの放置が大きな原因となるため、日常の清掃が最も効果的な予防策。営業前後には床や棚の拭き掃除、ゴミの処理を徹底し、衛生的な環境を維持しましょう。
まずは、毎日の清掃を徹底することが基本です。掃除の記録表を用意し、誰がいつ・どこを掃除したかを可視化しておくと管理がしやすくなります。
また、月に1〜2回の防虫・防鼠点検や、隙間・配管周りの封鎖なども効果的です。
害虫が発生すると、商品の信頼性が一気に低下するリスクがありますので、トラブルを未然に防ぐためにも、予防と点検を日常業務に組み込んでおきましょう。
スタッフ全員で守る! 衛生管理の基本と実践ポイント
販売所や加工施設を運営するうえでは、日常的な衛生管理をルール化して実践する「衛生管理計画」が重要です。
具体的には、作業区域の区分け、清掃スケジュールの作成、設備点検の頻度などを明確にし、全スタッフが共有できる体制を整えましょう。
衛生管理は、個人の意識だけに頼るのではなく、チーム全体で守るべきルールとして仕組み化することが大切です。とくに新人スタッフには、衛生基準の研修や実地指導を行い、早い段階で習慣づけることが望まれます。
また、衛生状態の記録や改善点の振り返りを定期的に行い、継続的にアップデートしていくことで、より安全で、消費者から信頼される青果販売の環境を実現できます。
衛生管理の基本を押さえたうえで、自分の販売スタイルに合った対策を一つずつ丁寧に取り入れていきましょう。
「買いたい」を引き出す! 売上UPのためのマーケティング戦略

青果販売を安定して続けるためには、商品の品質や衛生管理だけでなく、「売るための仕組みづくり」も欠かせません。
とくに小規模な直売やネット販売では、集客力や顧客とのつながりが売上に直結します。
SNSでの発信やネットショップの整備、ブランドの構築、そしてリピーターを増やすための工夫など、販売スタイルに合ったマーケティング施策を効果的に行い、販路拡大や収益アップを目指しましょう。
ネットとSNSを味方に! 集客につなげる発信と工夫
InstagramやX(旧 Twitter)などのSNSは、青果の色鮮やかさや産地の風景を伝えるのにぴったりのツール。定期的な投稿や、ハッシュタグを活用した情報発信によって、ファンの獲得や口コミの広がりが期待できます。
また、ネットショップは時間や場所に縛られず商品を販売できる強力な武器。「BASE(ベース)」や「STORES(ストアーズ)」などの無料ツールを使えば、手軽に販売を始められるのも魅力です。
こうしたネットツールを活用する際には、商品写真を明るく清潔感のあるものにし、説明文や保存方法を丁寧に記載することが、購入率アップのカギとなります。
運営後は、レビューへの対応や発送連絡の丁寧さも信頼度向上の重要なポイントになるので、顧客視点に立った対応を心がけることが大切です。
まずは、一件一件の注文を丁寧に扱い、信頼されるショップづくりを目指しましょう。
覚えてもらう・また買いたくなる! ブランドのつくり方
青果販売では、「どこで・誰が作ったのか」「どんなこだわりがあるのか」が信頼につながります。
地域性や栽培方法など、自分だけの特徴を明確に伝えることで、ブランド力が高まり、価格競争にも巻き込まれにくくなるでしょう。
また、ラベルやパッケージ、店舗のデザインに統一感を持たせることは、リピーターの定着につながるブランディングの第一歩。
視覚的な印象が強まることで、顧客の記憶にも残りやすくなるので、SNSや販売ページでも色使いやロゴのデザインを統一し、「見た目から記憶に残るブランドづくり」を意識してみましょう。
また買いたくなる!顧客との信頼を育てる伝え方
販売は一度きりで終わらせず、「次もまた買いたい」と思ってもらう仕組みづくりが大切です。
SNSでのコメント返信や、購入後のお礼メッセージ、簡単なアンケートなど、顧客と双方向のやり取りを行うことで信頼関係を深める手法も効果的でしょう。
とくに、直売所やマルシェなどでは、会話の中で「おすすめの調理法」や「今が旬の食材」を紹介するなど、ちょっとした工夫でファン化が進みます。
特典付きのLINE登録やポイントカードを導入すれば、再訪率アップも期待できますので、まずは身近なコミュニケーションから始めてみましょう。
万が一に備える! 青果販売のリスク対策と保険の考え方

青果販売では、日々の業務や取引の中で、さまざまなリスクと向き合う場面があります。
たとえば「品質に関するクレーム」「配送時のトラブル」「異物混入による返品」など、予期せぬ事態が発生することも少なくありません。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、衛生管理や表示の徹底といった日常的な取り組みが重要です。
さらに、万が一の事態に備えて、賠償リスクをカバーできる保険の活用も視野に入れておくと安心でしょう。
ここからは、青果販売における代表的なリスクとその対応策、そしていざというときのための保険の種類とポイントについてご紹介します。
食品トラブルを未然に防ぐ! クレーム対応とリスク対策の基本
青果は「生もの」である以上、鮮度や見た目の変化が避けられない商品です。そのため、購入後の傷みや異物混入など、品質に関するクレームが発生するリスクは常に存在します。
まず大切なのは、衛生的な取り扱いや保管を徹底すること。仕入れ時のチェック、販売時の温度管理、販売前後の清掃など、トラブルの芽を事前に摘む仕組みづくりを徹底しましょう。
また、万が一クレームが発生した際には、迅速かつ誠意のある対応が信頼維持の要になることも。状況を正確に把握し、丁寧に説明することで、多くの場合は顧客の理解が得られます。
トラブルをチャンスに変える視点も忘れず、対応履歴を社内で共有するなど、再発防止の仕組みづくりにもつなげていきましょう。
もしもの事態に備える! 生産者賠償責任保険とPL保険の活用
いくら注意していても、想定外のトラブルが発生してしまうことはあります。そのようなときに役立つのが、賠償責任保険の加入です。
とくに「生産者賠償責任保険」や「PL保険(製造物責任保険)」は、販売した青果や加工品が原因で消費者に損害が発生した場合の損害賠償をカバーしてくれる心強い存在です。
加入の有無で事業の継続性に大きな影響を与えることもあるため、補償内容や保険金額を比較検討し、自分の販売スタイルに合ったプランを保険会社と相談しながら選びましょう。
リスクに備えた準備ができていれば、万が一のときにも落ち着いて対応できます。安全・安心な青果販売を続けるために、リスクマネジメントの視点も忘れずに取り入れていきましょう。
まとめ
青果販売は、自家栽培や仕入れ、加工など販売スタイルによって必要な許可や手続きが異なります。
食品衛生法・食品表示法への理解を深め、衛生管理や設備の整備を事前に行うことは、安全・安心な販売の第一歩。はじめての方はもちろん、次のステップを目指す方も、基本をおさえたうえで着実に進めていきましょう。
青果の販売に興味がある方は、「オイシルキャリア」で自分に合った働き方を見つけてみませんか?
業界理解の深い専門エージェントが、あなたの強みや希望に合った求人をご紹介します。興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /