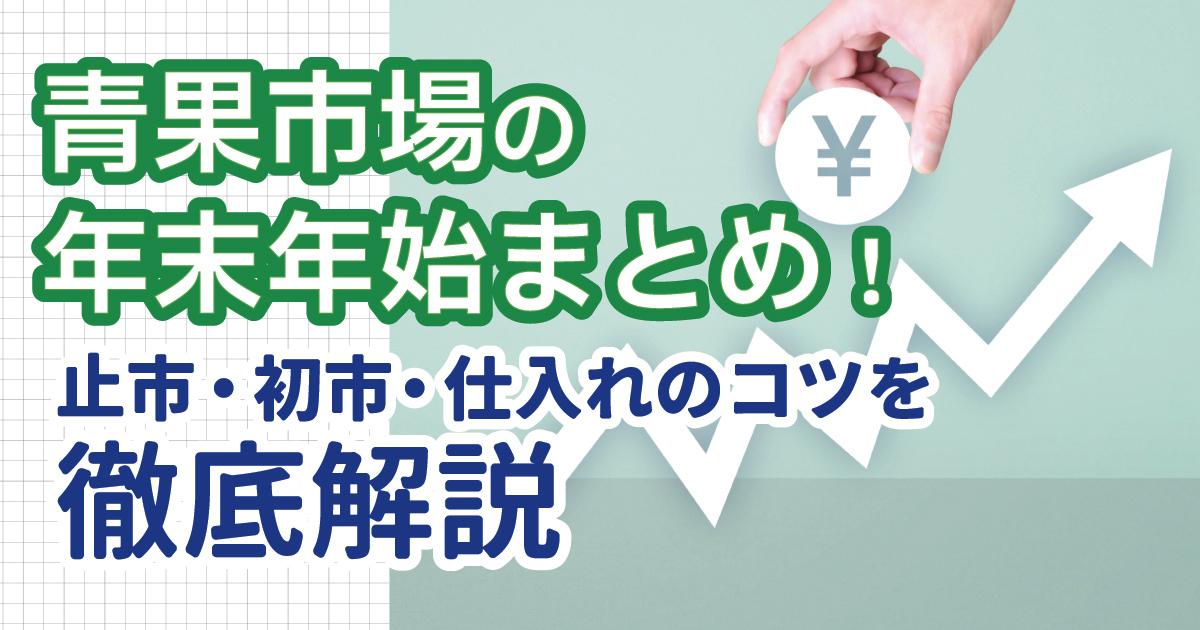年末年始の青果市場は、通常期とは異なるスケジュールと青果物の需要の高まりにより、仕入れや販売の判断が難しくなる時期です。
「止市(とめいち)や初市の動きは?」「いつ仕入れるべき?」「何が高騰する?」などなど。こうした悩みは、毎年現場で働く方々に共通のものではないでしょうか。
本記事では、2025年(令和7年)の市場カレンダーをもとに、現在の流通動向や価格変動の背景、仕入れ・販売の工夫をわかりやすく整理します。あわただしい時期を乗り切るための準備に、ぜひお役立てください。
青果市場の年末ってどのような感じ?「止市」と仕入れの注意点をチェック

年末にかけての青果市場は、青果物の需要と流通がピークを迎える1年の中でもとくに繁忙期にあたり、全国の卸売市場では物流や取引が活発化します。中でも重要なのが「止市(とめいち)」です。
止市とは、市場が年内最後の営業日として設定する“最終取引日”のこと。この日に向けて需要が集中するため、仕入れや輸送の混乱が起きやすくなります。
止市はいつ? 年末のスケジュールと市場の動きを読む
止市の日程は市場によって異なります。たとえば東京・豊洲市場では12月30日、大阪市中央卸売市場では12月29日が通例です。
年末の営業カレンダーは市場ごとに差があるため、自社の仕入れスケジュールや納品体制とずれが出ないよう、早めの確認が欠かせません。
止市の直前は、年末需要が一気に高まり、取引量が急増します。それに伴い相場が高騰しやすく、物流や納品も混雑する傾向にあります。
仕入れが遅れるとそのまま販売ロスにつながる可能性もあるため、必要な青果は余裕を持って手配し、輸送体制も含めた準備を整えておくことが重要です。
年末商戦を勝ち抜く! 仕入れで失敗しない青果と輸送の必勝法
止市が近づくと、市場の取引量がピークを迎え、一部の青果が高騰しやすくなります。
とくに、年末の食卓に欠かせない以下のような品目は、需要集中の影響で価格が跳ねることがよくあります。たとえば小松菜は例年12月末にかけて卸売価格が平時の2倍近くに上昇することもあり、根菜類や果物も同様に高騰傾向が見られます。
- 小松菜、春菊などの葉物野菜
- ごぼう、れんこん、にんじんなどの根菜類
- みかん、いちごなどの贈答用果物
これらは止市の直前ではなく、少し前倒しで手配するのが安全です。また、初市までの間、市場が休みに入ることを踏まえ、必要量は余裕を持って確保しておきましょう。
年末の売れ筋と在庫調整のコツ|欠品リスクを避けるには?
年末は、普段よりも動きの速い青果が増える時期です。とくに、おせちや鍋料理に使われる野菜や、家庭用・贈答用の果物などは短期間に需要が集中します。
一方で、止市以降は市場が休みに入るため、急な補充が難しくなります。在庫を切らしてしまうと、販売機会を逃すリスクも。とくに、取引先の営業再開時期と、自社の販売計画がずれている場合は要注意です。
欠品を防ぐためには、日持ちする青果は少し早めに手配し、動きの早い商品は需要予測に基づいて少し余裕を持って確保しておくのがポイントです。
止市前の仕入れでは「売れ筋を把握すること」と「多すぎず・少なすぎずの調整」が鍵となるでしょう。
青果市場の年始はどう動く?「初市」と仕入れのタイミングを見極めよう

年明けの青果市場も、通常営業とは異なる特別な流れがあります。中でも注目すべきは「初市(はついち)」です。
初市とは、新年最初の営業日であり、縁起物や贈答用青果の取引が活発になるタイミング。
新年最初の取引という特別な意味を持ち、市場の活気とともに価格も一時的に高騰する傾向があります。
仕入れ担当者にとっては、焦って動きすぎず、適切なタイミングを見極める冷静さが重要です。
年始「初市」の開催スケジュール! 最高値はいつ動く?
初市の時期は市場ごとに異なりますが、中央卸売市場では例年1月4日〜6日ごろに設定されます。
たとえば、東京都中央卸売市場の豊洲市場は1月5日、大阪市中央卸売市場は1月4日が初市となることが多いです。
この時期はまだ入荷量が少ないため、一部の青果に高値がつきやすい傾向です。縁起物や贈答用の品目はとくに価格が動きやすいため、仕入れは焦らず、在庫と相場の動きを見ながら進めることが大切です。
可能であれば、価格が落ち着く初市後の仕入れや、年末の前倒し調達も視野に入れましょう。
初市で価格が跳ね上がる青果は? 値上がりの理由と対策
初市では、縁起物や贈答需要のある青果が高騰する傾向があります。とくに以下のような品目は価格が跳ねやすくなります。
- 柑橘類(みかん、デコポン など)
- 高級いちご(あまおう、スカイベリー など)
- 山菜や伝統野菜(京野菜、ふきのとう など)
初市直後は流通量が安定せず、品薄になりやすいことも価格高騰の一因です。年末に生産・出荷が集中した影響で一時的に在庫が枯渇したり、休市期間中に十分な仕入れができなかったりすることが背景にあります。
さらに、年末年始にかけての寒波や降雪による交通遅延、配送業者の休業明けによる混乱なども重なり、予想以上の値動きが発生するケースも見られます。
こうした影響を避けるには、年末のうちに一部を確保しておく、または価格が落ち着くまで仕入れを待つといった判断も有効です。取引先との調整も含めて、柔軟な対応ができる体制を整えておきましょう。
初市で売れる青果はこれ! 仕入れ&出荷の成功ポイント
年始の売れ筋となるのは、正月料理や健康志向の需要に応じた青果です。
たとえば、春菊や三つ葉、京人参などはお雑煮やおせちに欠かせない食材として動きが早く、みかんやりんごといった定番の果物も家庭での消費が安定しています。
こうした需要を踏まえて仕入れを行う際には、まず取引先がいつから本格的に動き始めるかを事前に把握しておくことがポイントに。
初市では価格や在庫の状況が読みづらいため、最小限の仕入れにとどめ、実際の動きを見て追加発注を検討しましょう。
また、比較的日持ちする青果については、年末のうちに前倒しで確保しておくことで、年始の混乱を避けることができます。
年始の市場営業カレンダーに注意! 初市日を見落とさないために
初市は各市場によって違いがありますが、年によっては日程の並びや営業体制に注意が必要です。
とくに、初市日が日曜日に重なる年は、流通や営業再開の動きが例年より鈍くなることもあるため、十分な警戒が必要です。
仕入れ先や取引市場の稼働スケジュールを把握していないと、「注文したくても相手が営業していなかった」といったトラブルが起こる場合が起こりやすくなります。
年始の仕入れや配送計画を立てる際は、各市場や業者の営業日カレンダーを事前に確認し、ズレがないよう調整しておくことが重要です。
また、複数市場と取引がある場合は、それぞれの動きに応じて在庫の持ち方や納品の順序も柔軟に調整しましょう。
年始の仕入れは「カレンダーの読み方」ひとつで差がつきます。事前の確認と準備を丁寧に行いましょう。
年末年始の青果価格の変動要因|高騰を回避し、利益を確保する仕入れ術

年末年始は、青果物の価格が大きく動く時期。仕入れ担当者にとっては「いつ・どの品目を・どれだけ仕入れるか」の判断が、利益に直結する重要な局面といえます。
とくに、止市・初市前後は需要と供給のバランスが大きく崩れやすく、通常時にはない価格変動が発生することも。
ここからは、「なぜ高騰するのか?」「どの品目が安定しているのか?」「リスクを抑える方法はあるのか?」といったポイントを確認しながら、年末年始の価格変動について理解を深めていきましょう。
年末年始に青果が高騰する理由は? 相場の動きを読み解く3つの要因
年末年始は青果価格が大きく変動しやすく、仕入れの判断も難しくなる時期ですが、その背景には、主に次の3つの要因があります。
- 需要の集中
おせち・鍋料理・贈答用など、限られた日数に大量の需要が集中することで、相場が一気に跳ね上がる。 - 供給の減少
止市による流通停止や、生産現場の出荷調整によって、通常よりも市場に並ぶ量が減少傾向。 - 天候や物流の影響
寒波や降雪による遅延、トラックの混雑などが重なることで、供給が不安定に。
これらの要因が同時に起きると、わずかな需給のズレでも価格が大きく変動します。
相場の読み違いは、市場関係者の間でも毎年の課題とされています。価格の乱高下を回避するには、相場の傾向を早めに把握し、止市・初市の時期に過度な集中を避ける仕入れ計画を立てましょう。
相場が不安定でも安心! 価格の波を乗り切る仕入れ戦略
年末年始は、青果の価格が読みにくく、仕入れ判断が難しい時期。高値を避けるには、相場の動きを注視しながら、仕入れ方法を柔軟に使い分けることが大切です。
まず、有効なのが「安定品目を軸にした仕入れ」です。
たとえば、キャベツ、じゃがいも、玉ねぎなど、年末年始でも比較的価格が安定している野菜を中心に仕入れることで、コスト全体のバランスがとりやすくなるでしょう。
一方で、値上がりが予想される品目については、前倒しで年末に確保する/価格が落ち着くのを待って後ろ倒しで仕入れる/一定数量を予約・契約しておくといった対応策が有効です。
相場の波に流されない仕入れを実現するには、仕入れ価格の変動リスクを抑える視点で、「どこで、いつ、どれだけ仕入れるか」をあらかじめ想定しておきましょう。
仕入れ戦略を強化! 予約・代替品の活用で利益を守る工夫
年末年始は、仕入れたくても価格が合わない、数量が確保できないといったケースが少なくありません。そのようなときこそ、代替品や発注調整を活用した“守りの仕入れ”が効果を発揮します。
たとえば、高騰したいちごの代わりにりんごやバナナを提案したり、葉物が高いときには根菜で売場を補ったりといった、「カテゴリー内での置き換え」戦略が有効です。
味や用途が似た青果を上手に使えば、消費者の満足度を保ちつつ利益率を確保できるでしょう。
また、年末年始は実際の動きが読みにくいため、一気に仕入れるのではなく、段階的に発注量を調整することもポイントです。
小売や飲食の現場とこまめに連携し、売れ行きに応じて数量を見直すことで、過剰在庫や欠品のリスクを抑えましょう。
「仕入れる」だけでなく、「引く判断」も含めて、柔軟な対応ができるかどうかがこの時期の利益を大きく左右します。
年末年始に需要が高まる青果と売れ筋|需要予測を活かして売上アップへ!

価格変動に対応した仕入れができても、実際に売れる商品を見誤ればロスや在庫過多につながってしまいます。とくに年末年始は、季節や行事に合わせた食材の動きが明確に出るため、需要の波を正しく読むことが販売戦略のカギになります。
ここからは、年末・年始それぞれの売れ筋や傾向を整理し、「何を、どのタイミングで、どう売るか」を見極めるための視点をお届けします。
年末は“定番食材”が主役!おせち・鍋に強い売れ筋を押さえよう
年末は「年越し準備」の時期。家庭ではおせちや鍋料理が定番となり、定番食材のまとめ買い需要が高まります。
とくに動きが早くなるのは、小松菜や春菊といった鍋用葉物野菜、ごぼう・れんこん・にんじんなどの根菜類、さらには家庭用・贈答用のみかんやいちごなど。
これらの商品をサイズや価格帯の選択肢を広げて陳列することで、購買率を高める工夫ができます。
また、冷え込みが強まる地域では、鍋需要を見越して“土付き野菜”や“大容量パック”の需要も増える傾向があります。
前者は日持ちしやすく、後者はまとめ買いに適しており、どちらも冬場のニーズに合った商品といえるでしょう。
販促POPや売場演出など、販促の工夫を加えることで、購買率アップも狙えるので、仕入れと売場づくりは、地域性も加味して調整しましょう。
年始は “健康・正月らしさ”がカギ! 買い控えにも負けない提案を
年始はお祝いムードが残る一方で、消費者の動きが読みにくい時期です。外出を控える家庭が多くなる中でも、「正月らしい食卓」や「健康志向」を意識した青果は安定して動きます。
たとえば、三つ葉や京にんじんといった雑煮の具材、れんこんや里いもなどの縁起食材、またみかんやりんごなどの日持ちのする果物は、買い控えが起きやすい中でも売上を伸ばしやすいアイテムです。
加えて、近年では健康意識の高まりから、ブロッコリー、ほうれん草、長いも、きのこ類、さつまいもなど、体にやさしい食材も年始の売れ筋として注目されています。
販売側としては、年末の仕入れ分を年始にかけて活用できるよう在庫設計を工夫しつつ、季節感やヘルシーさを意識した陳列・販促POPでアピールしていきましょう。こうした提案が、年始の不透明な消費動向の中でも売上確保につながります。
年末年始における青果流通の注意点|鮮度と輸送の管理が仕入れ成功のカギ

年末年始の仕入れや販売で見落とされがちなのが、保管・配送といった“流通面のリスク”。
この時期は冷え込みや物流混雑の影響で、鮮度の低下や納品遅れ、在庫ロスが起きやすくなります。
せっかく仕入れた商品も、保存環境が悪かったり、配送タイミングを誤ったりすればロスやクレームの原因に。最後は、年末年始に特に注意すべき「保存」と「輸送」の落とし穴と、その対策を紹介します。
品質管理・鮮度保持のプロが実践! 長持ちさせる保管テクニック
寒さが厳しい年末年始は、一見保存しやすそうに見えて実は青果が傷みやすい時期。低温障害を起こしやすい野菜(なす、きゅうりなど)は5〜10℃前後、冷暗所向きの根菜類(ごぼう、にんじんなど)は10〜15℃程度が保管の目安です。
また、加湿器や新聞紙での乾燥対策、ダンボールの通気穴の向きなど、ちょっとした配慮でも日持ちが大きく変わります。
とくに売れ筋商品はストックしがちですが、仕入れすぎ=ロスのもと。在庫量は日々の販売予測と連動して調整しましょう。
年末年始の輸送リスクを回避! 計画的な配送調整を
年末年始は、トラック不足や納品集中、道路の混雑などにより、予定通りの配送が難しくなるケースが多発します。
とくに初市直後は配送業者も再始動のタイミングと重なり、青果の温度管理や納品時間のズレがトラブルにつながることも。
事前に取引先や物流業者とスケジュールをすり合わせ、配送予約の確保、ルートの再確認、納品時間の柔軟対応などを徹底しましょう。
また、配送当日のトラック手配漏れや代替便の確保にも目配りが必要です。
万が一に備えて、一部の商品は地場調達や店舗配送で補うプランBも用意しておくと安心です。
まとめ
年末年始は、青果市場のスケジュールや価格、流通が大きく動く特別な時期。止市・初市のタイミングを見誤れば、仕入れの失敗がそのままロスや機会損失につながるため、事前の準備が何よりも重要です。
本記事では、止市や初市のスケジュール、売れ筋傾向、相場の変動要因、そして物流や保存に関する注意点までを網羅して解説してきました。
混乱しがちな時期だからこそ、営業カレンダーや需要予測をもとに、仕入れ・販売を計画的に進めることが成果を左右します。市場関係者や仕入れ担当者の方々にとって、少しでも安心材料となれば幸いです。
📢 生鮮業界で働きたい方へ! 求人情報なら「オイシルキャリア」
🌱 生鮮業界に特化した求人を探すなら、業界専門の求人サイト「オイシルキャリア」の活用がおすすめです。専門のスタッフが丁寧にサポートいたしますので、効率よく就職・転職を目指したい方は以下をチェック!
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /