企業プロフィール

角上魚類ホールディングス株式会社
所在地:新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20
事業内容:鮮魚小売業(ロードサイド型大型店舗)、飲食事業等
従業員数:1,279名(正社員650名、準社員・パート629名)
店舗数:21店舗(2024年度)
年間売上:約450億円(2024年実績)
企業理念:「買う心 同じ心で 売る心」
一店舗で20億円超を売り上げる店舗もある鮮魚専門店、角上魚類。
「買う心 同じ心で 売る心」という理念のもと、“質で日本一の魚屋”を掲げ、全国でも類を見ない売上と組織力を誇る。
売上よりも“質”を追求する経営の背景には、従業員一人ひとりを育て、支える人事の仕組みがあるのだ。
今回は、同社の人事部長 針谷氏に、会社の成り立ちや理念、働き方、育成制度、そして出店戦略と求める人物像についてお話を伺った。
※ 質問に続く言葉は針谷氏のもの、「――」はインタビュアーのものとして記載。
Q1. まずは角上魚類について教えてください。どのような特徴や理念を持つ会社なのでしょうか?
針谷氏: はい。現在、関東甲信越を中心に21店舗を展開しておりまして、昨年度の売上は約450億円です。1店舗あたりの平均売上で見ると、20億円を超えるような規模になっています。
―― すごい規模ですね。1店舗の水産だけで20億円超えというのは、鮮魚専門店の中でもかなり珍しいと思います。
そうですね。1店舗当たりここまでの売上規模を出している会社はあまり多くはないと思います。
当社には「買う心 同じ心で 売る心」という理念があります。これは五・七・五の形で非常に覚えやすく、社内でも長く大切にされてきた言葉です。
この理念とともに「4つのよいか」といって、「鮮度はよいか」「値段はよいか」「配列はよいか」「態度はよいか」。この4点をまず徹底していこう、という店舗運営の原則が当社の店作りのベースとなっています。
―― 現場での実践が、理念の言葉に結びついていったわけですね。
はい、そうですね。その「4つのよいか」で“値段が良いか”といっていますが、我々はディスカウント業態ではないんです。
なので、「他社よりも品質のクオリティが高い、値段で想像していた以上にクオリティが高い」というようなところを目指している、という意味ですね。
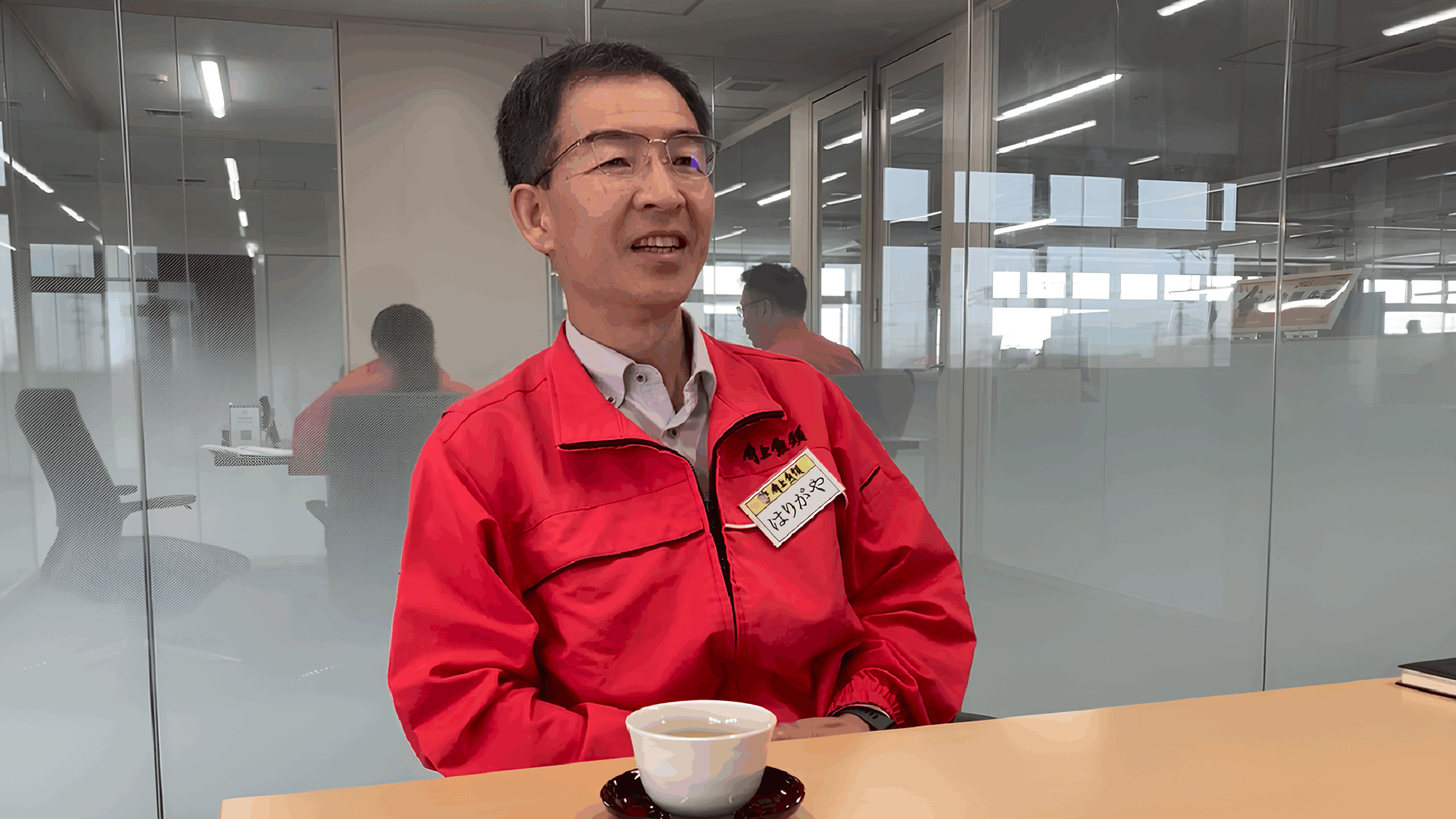
角上魚類の「買う心 同じ心で 売る心」という言葉には、まず現場の実践があり、それを後から誰もが納得できる形で言葉にしてきた歴史がある。最初から掲げられた理想ではなく、日々の商売を通じて自然と社内に共有されてきた価値観が、やがて一つの言葉にまとまっていった。真剣に商売と向き合ってきた時間が、この理念に宿っているように感じられる。
“質の日本一”という方針が、社員・商品・経営のすべてに浸透し、現場と理念がかけ離れていないからこそ、この言葉は今も生きた指針として受け継がれているのだろう。
Q2. 店舗での働き方には、どのような工夫があるのでしょうか?
針谷氏: 当社では、鮮魚の対面、鮮魚のパック、刺身の3部門に加えて、寿司、マグロなどを含めて、全部で11の部門を設けています。
冷凍や魚卵、鮭鱒(けいそん)、塩干珍味、惣菜といった商品も、それぞれ独立した部門として専門的に管理しています。
―― 鮭鱒が独立部門というのは珍しいですね。なにか特別な理由があるのでしょうか?
そうですね。当社は新潟が発祥ということもあって、鮭鱒や魚卵の消費量が多い新潟ならではの需要にしっかり応えていくために部門化しています。
店舗でのバラ売りのサケも年間1,000万切れ以上販売しており、とても評判が良いんです。
―― 地域性を踏まえた部門構成からも、御社のこだわりが伝わってきます。接客や部門ごとの体制といった、現場の運営スタイルにも特徴があると伺いました。
はい、対面販売の部門では、ただ魚を並べるだけでなく、お客様にその日入荷した魚をおすすめしたり、調理法の提案をしたりといったコミュニケーションも大切にしています。
多くのお客様からは魚のおろしを依頼されることもあり、そうしたリクエストにもその場で対応しています。
仕入れは魚種ごとのバイヤーが専門で担当していて、毎朝、豊洲と寺泊のバイヤー同士で情報交換を行いながら価格や品質を見て判断しています。
バイヤーと店舗のコミュニケーションは密に取っていますので、情報の行き違いは少ないですね。
加工部門では、鮮魚パックや刺身、寿司など、それぞれで扱う魚の種類や切り方が異なります。
特に寿司部門では、ネタの切り方や提供方法に専門性が求められます。また、マグロ部門では、解体・スライス・冊取りといった技術に加えて、地中海産の養殖ものから国産の天然ものまで複数種類を扱う奥行きのある商品構成が特徴です。
一方で、冷凍、魚卵、鮭鱒、塩干、珍味といった部門では、技術的な加工よりも、在庫管理や売場づくり、計画的な発注・補充といった力が求められます。
商品をより魅力的に見せるためのトレー詰めの仕方など、現場での工夫が売上に直結する点もあり、決して難易度が低いわけではありません。
むしろ生鮮部門とは違うスキルが必要とされるため、管理職社員もこれらの部門を経験しているものも多いです。


角上魚類の店舗構成には、地域に根ざした食文化への理解と、鮮魚への強いこだわりが反映されている。そして、提供する商品への目利きと同じくらい、その魅力を届ける現場の体制づくりにも力を注いできた。
仕入れを専門のバイヤーに任せることで、店舗スタッフはお客様に向き合うことに専念できる。こうした体制のもとで丁寧に積み重ねてきた接客が、お客様との信頼を育み、角上魚類がここまで成長してきた確かな土台となっているのではないだろうか。
Q3. 働きやすい職場づくりのために、店舗ではどのような体制が整えられているのでしょうか?
針谷氏: 勤務時間については、時差出勤を取り入れています。早番は朝7時から16時、遅番は12時から閉店作業までといった時差出勤シフトで運用しており、閉店時間は店舗によって異なりますが、だいたい19時から20時の間です。
こうした工夫により、従業員への業務過多をできる限り減らしています。
―― つまり、こういった体制によって、長時間労働を防ぐことにもつながっているわけですね。
はい。特に平日は、残業なしで帰れている方も多くいます。もちろん、週末は朝6時半や7時からの出勤になることもありますが、それでも売場の動きに合わせて、必要なときに早出や残業があるという感じですね。
有給も取りやすくて、昨年度の取得実績でいうと平均11.8日でした。
管理職についても、店長・店次長・副店長と、各部門の部門長を配置しております。そうすることで、店長が不在でも店舗が回るような体制を整えています。副店長は2人配置している店舗も多いですし、店次長・店長を含めて役割を分け合うことで、「●●さんがいないから仕事がわからない」といったことが起きないようにしています。また、時差出勤によって残業もある程度コントロールできています。
―― 特にこの業界の管理職(店長・副店長)は有給が取りづらいと思うのですが、有給取得実績11.8日とはすごいですね。
ただ、4人の管理職体制になると、権限が分散してしまい、統制が難しくなるということはありませんか?
それは常に課題として捉えています。やはり、店長、店次長、副店長1,2名との面談や研修を通して、しっかりコミュニケーションを取ってもらうようにしています。その上で、社員に落とし込んでもらっています。

管理職4人体制や時差出勤、役割分担の工夫によって、角上魚類では「現場に頼りきらない体制づくり」が着実に進んでいる。特定の管理職に負担が偏ることなく、誰かが休んでもスムーズに業務が流れる仕組みが整っている点は、同業他社と比べても大きな特色だ。
役割を分け合い、互いに支えながら店舗を動かしていく。中間管理職が無理なく働けるこの体制こそが、信頼される現場づくりの要になっている。
Q4. 新人育成や研修制度は、どのように整備されていますか?成長を支える教育体制や制度について教えてください。
針谷氏: 角上魚類では、部門ごとのプロフェッショナルを育てることを重視しており、それぞれの業務に応じた専門的な育成体制を整えています。
新人教育としては、入社から半年間は「指導パートナー」と呼ばれる若手社員がバディを組み、新入社員のメンターとしての機能と、技術やスキルの両面から支える役割を担っています。
基本的には入社3〜4年目の社員が担当しますが、場合によっては部門長が兼任することもあります。
また、新卒社員向けには入社後すぐに5日間の座学研修を本社で行っており、ビジネスマナーや業務の基礎を学んでもらっています。
―― キャリアアップに向けた研修制度は、どのようになっているのでしょうか?
キャリア形成においては、等級制度に基づいた「キャリアアップ研修」を用意していて、その年ごとにテーマを設定しています。
たとえば「巻き込み力」を発揮するための研修、アサーティブコミュニケーションなど、実践力のある内容を、人材育成課が中心となって企画・運営しています。
あとは「リーダーシップ研修」ですね。これは、部門長から副店長・店次長・店長といった店舗管理職へステップアップする前後の層を対象に行っています。
昇進の順番としては、一般職から部門長へ進み、その後、副店長、店次長、店長と段階的に上がっていく形になります。
店舗管理職になると帽子の色も変わり、社内でもその役割が一目で分かるようになっています。
―― 人事制度の面で、特にユニークな取り組みはありますか?
最近では、本部の管理職に対して360度評価を導入しました。バイヤーやスーパーバイザー、人事、エリアマネージャーなどが対象です。
より本部の機能を高めるという意味合いで、今年からスタートした制度です。魚屋業界ではまだあまり例がない取り組みだと思います。

新人育成から管理職の評価に至るまで、角上魚類では“段階的に人を育てる”仕組みが丁寧に設計されている。研修制度と実地指導がうまく組み合わされ、役割ごとに必要なスキルが確実に身につくようになっているのが特徴だ。
一方で、評価制度においても形式だけで終わらせない工夫が見られ、360度評価の導入に象徴されるように、成長を支える“仕組みの更新”も着実に進められている。
Q5. 角上魚類でのキャリアは、どのように築いていけますか?入社後の仕事内容や成長のステップについて教えてください。
針谷氏: 入社後は、経験の有無によって配属部門が変わることが多いです。魚を扱った経験がある方は鮮魚部門から、そうでない方は惣菜部門からスタートするケースが多いですね。
たとえば、フライヤーでの揚げ物など、比較的入りやすい工程から始めてもらうことが多いです。
ある程度経験がある方で鮮魚部門に入った場合は、アジやイワシといった青魚を下ろす作業からスタートします。お刺身やお寿司に使う分もあるので、朝から夕方までずっと魚をおろしているような日もあります。
―― 経験の有無に応じて無理のないスタートができるんですね。ちなみに、その後の部門の異動は、どのように決まるのでしょうか?希望を出すこともできるのでしょうか?
部門の異動については、店長の裁量で戦略的に決めることが多いです。
たとえば、入社3年目くらいで「次は寿司をやらせたい」というように、将来を見据えた配置をしています。多能工化*を進めていて、管理職になるためには複数の部門を経験していることが強みになると考えています。
※多能工化… 一人の従業員が複数の業務をこなせるように、スキルや能力を向上させる取り組み。
実際、今は社内でも「いろいろな部門を経験しておこう」という意識が広がっています。管理職になったとき、それが強みになることを、みんなが理解しているんです。
部門の異動に関しても、もちろん自分から希望を出すこともできます。「新しいことにチャレンジさせてくれない」と不満を溜め込むのではなく、自分の希望を伝えることが大事です。
当社はそうしたことを言いやすい雰囲気があると思いますし、やる気や意欲を受け止めて、チャレンジできる、してもらう文化があると思います。
―― 意欲や希望をしっかり受け止めてくれる環境なんですね。昇格の判断については、やはり経験年数が重視されるのでしょうか?
部門長になるには、経験年数だけでなく、「やりたい」という気持ちの強さを店長が見て判断することが多いですね。
最近では、意欲ある若手を積極的に抜擢し、経験の長い社員がその部門長をサポートする形も増えています。単に経験年数ではなく、チャレンジ精神を重んじる文化が根づいているんです。


角上魚類では、経験の有無に応じた適切なスタートラインが用意されており、無理なく技術を身につけられる環境が整っている。
部門間の異動や昇進も、単なる年数ではなく、意欲と対話を重視する方針が根づいており、自発的に動ける人には成長の機会がしっかりと開かれているのだ。経験の有無にかかわらず、意志を持って挑戦する人にとって、角上魚類は確かな成長の場となりうるのではないだろうか。
Q6. 角上魚類の今後の展開について教えてください。出店戦略や新たな取り組みなど、差し支えない範囲で伺えますか?
針谷氏: 角上魚類では、出店についてはかなり慎重に判断しています。目指しているのは、ただ店舗数を増やすことではなく、教育体制とのバランスを取りながら、質を保った成長を実現していくことです。
現在予定されている出店としては、2026年2月に「狭山店」がオープン予定です。
出店方針としては、スーパーマーケット内のインショップではなく、ロードサイド型の独立店舗を基本としています。車で来店されるお客様が多く、通いやすさという点でも適していると考えています。
出店にあたっては、その地域ごとの食文化や買い物スタイルも丁寧に見極めています。単に店舗を展開するのではなく、土地の嗜好に応じた売場づくりを目指すのが角上魚類の姿勢です。
「どこでも同じものを売る」のではなく、「地域に求められる魚屋でありたい」という思いが、出店判断の根底にあるのです。
―― 出店にも“質の追求” が貫かれているのですね。
ええ、そうですね。無理に出店して教育が追いつかなくなってしまっては本末転倒ですから。だからこそ、出店のタイミングはしっかりと見極めています。

角上魚類の出店戦略は、単なる拡大ではなく、「人を育てられる規模」で確実に歩を進める姿勢が印象的だった。
ブランドの信頼感を損なわずに、地域と育成の両方に根を張っていく堅実さこそが、同社の持続的な成長の鍵なのだろう。
Q7. 最後に、角上魚類ではどのような人材を求めていますか?応募を検討している方へのメッセージをお願いします。
針谷氏: やはり一番は、「やってみたい」という意欲ですね。魚の知識や技術は、入社してからでもしっかりと身につけられますから、最初から完璧である必要はまったくありません。
当社では、「やりたい」と声に出せる人をしっかりと評価しますし、実際に若手を抜擢する場面も増えています。経験の長い社員がそういった若手を支える体制も整っているので、年齢や経歴に関係なく、どんどん挑戦してほしいですね。未経験の方も、ぜひ応募して欲しいです!
―― 御社に転職してきた方から「ここが違うな」など、よく言われることはありますか?
よく言われるのは、やはり「物量の多さ」ですね。まさか一日でこんなに売れるとは思わなかった、と驚かれることがよくあります。
それと「客数の多さ」も印象的なようで、開店前からお客様が並んでいる光景は、他社ではあまり経験がないと言われます。年末などは特に顕著ですね。
あとは「労働環境の良さ」。物量が多いので残業時間が長いと思われている方が多いのですが、平均残業時間は22時間です。
また、「教育環境がある」という点も驚かれます。「技術水準が高くて大変そう」と見られることもありますが、当社には育てる仕組みがしっかり整っています。
その仕組みの下、物量をこなすことで自然と力がついていきます。たとえば、魚のおろしが早くなる、歩留まりがよくなる、身割れが起きにくくなるといった形で、着実にスキルアップしていきます。
なので、たとえ技術がまだ未熟でも、入社後にしっかりと力を伸ばすことができますし、1店舗あたり20〜30名の社員がいるので、技術の高い先輩がすぐそばにいて、学びの機会もとても恵まれていると思います。
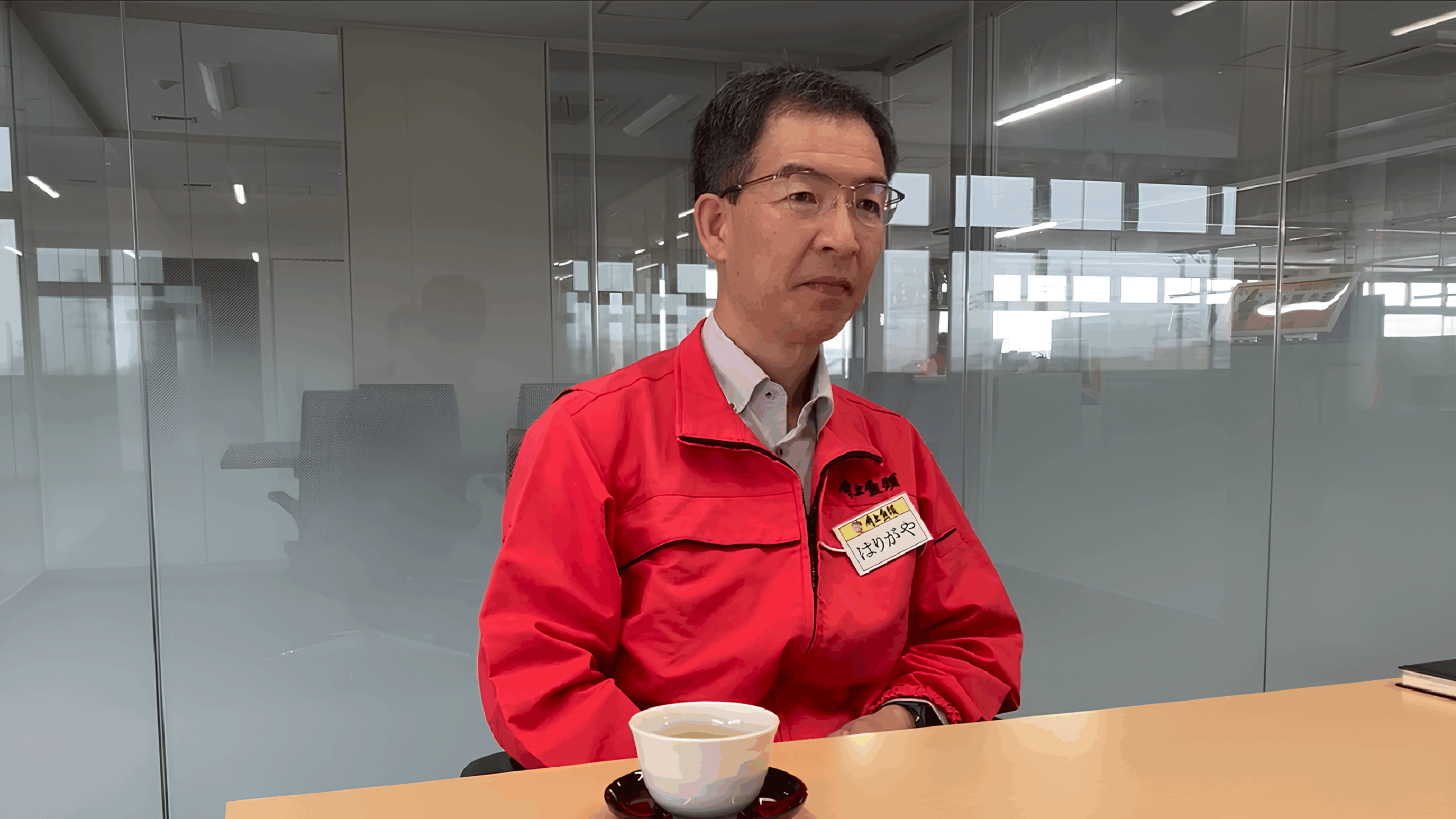
角上魚類が求めているのは、スキルや経験よりも「挑戦したい」というまっすぐな気持ちだ。売場で魚をさばき、提案し、売る。その一つひとつの仕事に、誇りを持てる人にこそ向いている環境だと感じた。
なお、このような方にはとくにおすすめしたい企業だ。
- 魚のプロフェッショナルになりたい方
- 手に職をつけて長く働きたい方
- 経験よりも意欲で評価されたい方
- 自分のアイデアで売場を動かしてみたい方
- 現場のスピード感や活気が好きな方
どれかひとつでも「当てはまるかも」と思えたなら、角上魚類という職場がきっと自分の挑戦を歓迎してくれるだろう。
経験の有無に関係なく、「魚を通じて誰かの暮らしを豊かにしたい」と願う人にとって、角上魚類は最良の一歩になるはずだ。








