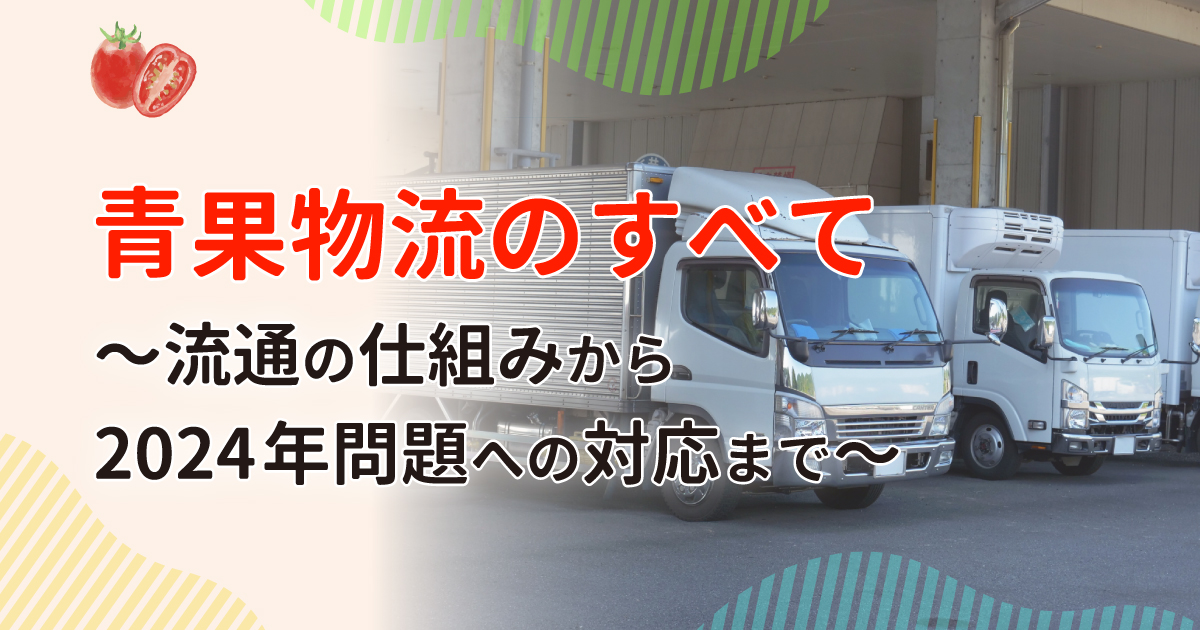新鮮な野菜や果物が、日々当たり前のように店頭に並ぶ。その裏側には、スピードと精度が求められる「青果物流」の仕組みがあります。
生産地から消費地へ。多くの人と工程を経て動くこの流れは、今まさに大きな転換点を迎えています。
2024年問題の影響を受け、青果物流はどのように変わっていくのでしょうか。
本記事では、青果物流の基本的な流れから、品質保持のポイント、そして今後の課題と対応策までを詳しく解説します。
仲卸業者やスーパー、飲食店など青果を扱う事業者の方はもちろん、物流業界の関係者にとっても役立つ情報をお届けします。
青果物流の現状を理解し、これからの変化に備えるための一歩を踏み出しましょう。
市場・仲卸・物流センターの役割とは?青果物流の基本を押さえよう

青果の物流は、市場や仲卸を経由して小売店や外食産業へと届けられますが、野菜や果物は生産地ごとに収穫量や出荷時期が異なるため、安定供給には柔軟な流通体制が欠かせません。
この流通の過程において、市場や仲卸は、単なる通過点ではなく、青果の安定供給を支える要。適切な仕分けや品質管理、さらには保存・輸送時の温度管理を徹底することで、新鮮な青果を消費者のもとへ確実に届ける調整役として機能しているのです。
まずは、市場・仲卸・物流センターのそれぞれの役割と、青果物流の仕組みを詳しく見ていきましょう。
流通経路と青果物仲卸・市場の役割
青果物は産地から集荷されると、まず集約拠点となる市場に運ばれます。
市場では、仲卸が集めた大量の青果物を、小売店や飲食店などの注文内容に応じて種類や数量ごとに仕分けし、各取引先に向けて効率よく出荷しています。
仲卸が取引先ごとの注文に応じて仕分けや出荷を担うことで、市場内での情報共有や作業の分担がスムーズになり、輸送の手配も的確に進められます。
その結果、急な注文変更や数量の調整といった状況にも柔軟に対応できる体制が整うのです。
また、近年は、小ロット・多頻度出荷の要望が高まり、それに対応するため共同配送や中継輸送方式を取り入れる事業者も増えています。
こうした取り組みによって、さらなるコスト削減が可能になり、輸送時間の短縮に。その結果、お客さまに届く野菜や果物の鮮度も向上しています。
物流センターにおける商品仕分けと出荷の流れ
市場や仲卸から送られた青果物は、物流センターに集められ、各店舗や施設ごとに仕分けされます。
このような仕分け作業では、青果の種類ごとに適切な温度帯での管理や滞留時間の調整が必要不可欠。すぐに配送に回すものは出荷スペースへ、保管が必要なものは冷蔵や定温の設備へ移すなど、それぞれの特性に合わせた管理が行われています。
実は、こうしたプロセスの効率化には、ITシステムの活用が欠かせません。在庫数や商品情報をリアルタイムに共有することで、作業負担を軽減し、人的ミスを防ぐだけでなく、出荷のスピードと精度も向上するのです。
その結果、各トラックへ積み込まれた青果物は、ルート配送や当日発送のスケジュールに従い、新鮮な状態を保ったまま消費者のもとへ。
迅速かつ適切に届けられることで、小売店や飲食店の仕入れ計画もスムーズに進み、需要に応じた安定供給が実現できるのです。
「温度管理・加工・トレーサビリティ」青果の品質を守る3つの視点

青果を新鮮な状態で流通させるには、気温や湿度の変化に敏感な青果物の特性をふまえた、きめ細やかな管理が必要です。とくに重要なのが、「温度管理」「加工技術」「トレーサビリティ」の3つの視点です
● トレーサビリティとは
食品が「いつ・どこで・どのように生産・加工・流通されたのか」を追跡できる仕組み。万が一の品質トラブルにも迅速に対応できる体制づくりに欠かせない。
① 定温輸送と予冷の技術
青果物は温度変化によって品質が大きく左右されるため、低温輸送や予冷技術が品質保持の鍵となります。
とくに、輸送前に青果物をあらかじめ冷やす予冷技術の進歩により、野菜や果物の成熟や劣化の進行を遅らせることが可能になりました。
これにより、長距離輸送や小ロット多頻度配送でも鮮度を保ちやすくなっています。
また、近年では、コントロールド・アトモスフィア(CA)技術を活用した冷蔵倉庫の導入も進み、従来の冷蔵保存よりも長期間にわたって青果の品質を維持できるようになりました。
コントロールド・アトモスフィア(CA)技術とは、貯蔵庫内の酸素や二酸化炭素などのガス組成を調整し、適切に管理することで農産物や食品の鮮度を保持する技術。です。これにより、青果物の呼吸を抑え、より長く鮮度を維持できる環境を実現しています。
これらの技術を適切に組み合わせることで、生産から消費までの品質管理が一層強化され、消費者のもとへより高品質な青果を届けることが可能になりました。
② カット加工とパッケージングの技術
消費者のライフスタイルの変化や時短志向の高まりにより、カットフルーツや野菜カット加工品の需要は年々増加しています。
とくに、都心部で働く家庭では、健康志向の高まりとともに、手軽に食べられるカット野菜やフルーツが重宝されています。
このような加工品は、洗浄・カット・パッケージングまでの一連の工程を衛生的かつスピーディに行う必要があり、そのためには自動化や温度・湿度管理を含む効率的な生産ラインの整備が欠かせません。
また、加工後の青果物は切り口からの劣化が進みやすいため、空気や水分を適度に遮断する包装技術の良し悪しが商品の鮮度を左右します。
そのため、フィルム包装や真空パックなど、用途に応じた適切な包装方法を選ぶことが重要となります。
その他、細かな規格やサイズ分けを行うことで、輸送効率や店頭での陳列効率も向上し、流通全体の無駄を削減する効果も期待できます。
こうした工夫を積み重ねることで、鮮度を保ったまま安定供給が可能となり、消費者の利便性向上にもつながるのです。
③ トレーサビリティと履歴の管理
青果物の安全性と品質を守るためには、トレーサビリティの確立が不可欠です。
生産地や輸送経路、保管期間などの情報を追跡できるシステムを導入することで、万が一のトラブル発生時にも迅速な原因追及や回収が可能になります。
とくに、輸入農産物は海外の農場や港湾を経由するため、管理が複雑になりがち。これに対応するために、バーコードやRFIDを活用した記録管理を導入し、各国の規格に適応することで、国内品と同等の品質を確保する取り組みが進められています。
こうした管理体制の充実は、消費者に安心感を提供するだけでなく、企業にとってもリスクヘッジの強化につながる重要な取り組みといえるでしょう。
2024年問題で青果物流はどう変わる?人手不足への対応策

働き方改革関連法に伴う2024年問題により、青果物流のオペレーションは大きく変わる可能性があります。
とくに、トラックドライバーの残業規制が強化されたことで、今後人手不足がさらに深刻化し、従来の長距離輸送の維持が難しくなることが懸念されています。
青果物は鮮度が生命線であるため、輸送時間の確保や、限られた時間内での効率的な配送がこれまで以上に重要になるでしょう。
こうした課題に対応するため、中継拠点を活用した共同輸送や配送ルートを最適化するITシステムの導入など、新たな取り組みが進められています。
これらの手法を取り入れることで、労働環境の変化に対応しながら、青果の安定供給を維持することが期待されています。
当日配送への対応と、業界全体で進む物流改革
青果物流では、店舗や飲食店から「当日に欲しい」という要望も少なくありません。
しかし、2024年問題によりトラックドライバーの残業規制が強化され、限られた人員と時間で即日発送を維持することは難しくなってきています。青果は鮮度が命であるため、迅速かつ効率的な配送体制の構築は喫緊の課題となっています。
こうした状況に対応するため、物流現場や業界全体で以下のような対策や取り組みが進められています。
● 共同配送
複数の企業がトラックや配送網を共有し、同じ納品先への配送を効率化する方法。積載率の向上やドライバーの稼働削減につながります。
● クロスドッキング
倉庫で保管せず、入荷した商品をすぐに仕分けて出荷する方式。保管スペースや時間を省き、スピーディな配送が可能になります。
● 拠点分散
物流拠点を複数の地域に分けて配置することで、トラックの移動距離を短縮し、ドライバーの負担を軽減します。
● 配送ルートの最適化・積載率の向上
効率的なルート設計や車両の積載効率を高めることで、限られた時間内でも多くの配送をこなせる体制を構築。
● AIや車両配置技術の導入
ルート最適化やスペース管理を自動化することで、人的負担を軽減しながら安定供給を実現します。
これらの取り組みによって、青果物流における即日対応の難しさを補いながら、労働環境の改善と安定的な供給体制の両立が期待されています。
いま注目される「ベジロジナカジマメソッド」の可能性とは
このように、さまざまな物流効率化の取り組みが進められる一方で、現場レベルでの作業負担をどう減らすかも重要な課題となっています。
作業時間の短縮や省力化を実現するには、現場に即した仕組みやノウハウの確立が欠かせません。
その実践例として、近年業界内で注目を集めているのが「ベジロジナカジマメソッド」です。
「ベジロジナカジマメソッド」は、青果物流の現場における改善策のひとつであり、青果物の特性に応じた温度管理や仕分けシステムを導入することで、作業の標準化を図ることを目標としています。
その結果、新たなスタッフでも短期間で作業スキルを習得しやすくなり、原材料の調達から消費者への納品までの全体の所要時間(トータルリードタイム)を短縮できるようになりました。
さらに、長時間労働の是正と品質維持を両立するモデルとしても期待されており、業務の効率化や人材確保の面でも高い効果が見込まれています。今後、他の現場でも導入が進む可能性のある実践的な改善策といえるでしょう。
青果物流の現場から見る、これからの課題と展望

青果物流の現場では、鮮度の確保と効率的な供給を両立させるための取り組みが進められています。
今後の安定供給と業界全体の持続的な発展に向け、どのような対応が求められているのか、見ていきましょう。
青果物流の業務フローと現場での取り組み
青果物流の現場では、集荷から出荷、その後の検品や情報管理まで、各工程が明確に分けられ、効率的に運用されています。ここでは代表的な流れをステップごとに紹介します。
青果物は市場や生産地から集荷され、物流拠点に搬入されます。適切な温度・湿度で保管されながら、出荷に向けた品質確認が行われます。
顧客からの注文情報をもとに在庫を確認し、ピッキングリストを作成します。納品先やルートを考慮して、効率的な配送につながるよう設計されます。
商品のピッキングリストに従って仕分けを行い、配送先ごとに分けたのち、適切な温度管理がされた車両に積み込みます。
仕分け・積み込みを終えた商品は、店舗や市場、外食産業などの納品先へ出荷されます。配送中も温度が保たれるよう管理され、鮮度の維持が図られます。
こうした一連のステップを通じて、青果物流では「鮮度を保ちながら、確実に商品を届ける」ための基本的な流れが構築されています。
このほかにも、現場の負担軽減やミスの防止、納品精度の向上を図るために、多くの企業がITシステムの活用や作業効率化の工夫を取り入れています。
● 納品管理とITの活用
納品時間の正確性を確保するため、多くの企業ではリアルタイムの情報共有が可能なITシステムを導入しています。
配送状況の把握や到着時刻の予測が可能となり、取引先との連携精度が向上しています。
● 検品・棚卸しの効率化とミス防止
倉庫や配送拠点では、ハンディターミナルやRFIDタグを活用することで、検品や棚卸し作業のスピードと精度が向上しています。
誤出荷の防止や在庫管理の精度強化にもつながっており、現場の負担軽減にも効果を発揮しています。
車両不足にどう対応する?3PL活用と車両確保の工夫
青果物流では、鮮度を維持しながら効率的に輸送するために、適切な車両の確保が欠かせません。
とくに、大規模な物流企業では、冷蔵・冷凍・常温など複数の温度帯に対応した車両を保有し、それぞれの特性に応じた輸送体制が整えられています。
一方で、すべての企業が自社で必要な車両を揃えるのは現実的ではありません。
このような背景から、外部リソースを活用して物流体制を補強する動きが加速しており、その代表例が、業務効率化にもつながる3PLサービスの導入です。
● 3PL(サードパーティ・ロジスティクス)とは
物流業務を専門の外部業者に委託する仕組みのこと。配送や在庫管理、車両手配などをアウトソーシングすることで、業務効率化やコスト削減につながる。青果物流では、繁忙期の車両確保や広域配送への対応策として活用されている。
青果物流でも、繁忙期の車両不足に備えて3PL業者と契約し、必要なタイミングで冷蔵・冷凍車を確保する取り組みが広がっています。
また、全国規模での配送ニーズに対応するため、自社だけで完結させず、3PLを活用して広範囲の輸送ネットワークを構築する企業も増えています。
さらに、ルート最適化システムや車両のシェアリングサービスなど、3PL業者が提供するサービスを取り入れることで、コスト削減と柔軟な配送対応を両立させる工夫も進んでいます。
こうした取り組みによって、青果物流の安定性や効率性は着実に高まりつつあります。
今後は、自社の車両運用と3PLのバランスをどう最適化していくかが、安定供給とコスト管理を左右する大きなポイントとなるでしょう。
仕入れ・販売・配送の最適化を目指して
青果物流を最適化するためには、サプライチェーン全体を見渡す視点が欠かせません。
そのため、仕入れ段階での需要予測や在庫調整、販売チャネルごとに異なる基準を踏まえた商品ラインナップの設計など、各プロセスを相互に連携させる取り組みが求められています。近年では、これらを支えるITツールの導入も進んでいます。
たとえば、生産者と情報を共有することで、余剰在庫や欠品を防ぎ、採れたての青果を無駄なく消費地へ届けることができます。
また、AIを活用した需要予測システムや在庫管理ツールを導入すれば、日々の配送計画の精度が高まり、無駄のない効率的な物流が実現します。
今後は、ビッグデータ解析やAIによる予測技術がさらに進化し、青果物流の安定化と効率化は一層加速するでしょう。
まとめ
青果物流は、鮮度の保持と効率的な供給を両立させるために、日々進化を続けています。市場や仲卸、物流センターといった各機能が役割を果たすなか、働き方改革やITの活用が、今後の物流を支える重要な要素となっていくでしょう。
2024年問題により人手不足が懸念される一方で、共同輸送や3PLサービスの導入が進み、より柔軟で安定した体制の構築が加速しています。
これにより、消費者にとっても安心でスムーズな供給環境が整えられつつあります。
今後は、AIやビッグデータなどの技術革新によって、さらなる効率化や高品質な物流体制が期待されます。その進化を支えるのは、新たな技術に対応できる柔軟な人材であり、青果物流の分野でも多様なキャリアの可能性が広がっています。
青果物流業界でのキャリアを考えている方にとって、今はまさにチャンスの時! オイシルキャリアでは、生鮮関連の求人情報が豊富に揃っています。
現場力を支える仕事に興味がある方は、今まさに成長する業界でのキャリアを築く絶好のチャンスです。ぜひご覧ください。
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /