日々の食卓や買い物で耳にする「生鮮食品」という言葉。しかし、その定義や表示ルールを正しく理解している方は多くありません。
生鮮食品は鮮度が最も重要である一方、法的な表示義務や、加工食品との区分など、知っておきたいポイントがいくつもあります。本記事では、生鮮食品の定義から特徴、表示ルールまでをわかりやすく解説します。
生鮮食品とは

スーパーの青果・鮮魚・精肉コーナーで目にする「生鮮食品」。日常的に使われるこの言葉の正確な定義と区分を理解しましょう。
食品表示基準における定義
生鮮食品の定義は単に「加工されていないもの」と思われがちですが、実際には多少の加工(カットやスライス)が施されていても、食品の本質が変わらなければ生鮮食品として扱われます。
重要なのは、調味料や添加物が加えられておらず、基本的に「生の状態」を保っているかどうかです。食品表示基準では生鮮食品を「加工食品および添加物以外の食品」と定義し、大きく3つに分類しています。
農産物は野菜や果物、穀類などを指し、水産物には魚介類や海藻類などが含まれます。畜産物には肉や卵などが該当します。
一般的には、野菜・果物、魚介類、肉類といった「生鮮三品」を思い浮かべる方が多いでしょう。これらは基本的に”生の状態”で流通しており、スーパーの青果コーナーや鮮魚コーナー、精肉コーナーなどで目にするものが該当します。
加工食品との違い
加工食品は、加熱・発酵・味付け・保存処理などで食品の性質や形態が変化したものです。一方、生鮮食品は、カットやスライスなどの簡易的な工程は行われても、添加物や調味料を加えていなければ”生のまま”とみなされます。
たとえば、キャベツの外葉をむいただけの丸ごとの状態はもちろん、千切りにカットしただけの野菜でも、調味料などが一切加えられていなければ「生鮮食品」です。
具体的には、丸ごとの野菜・果物としてトマト、きゅうり、りんご、みかんなどがあり、カットまたはスライスされた野菜・果物では千切りキャベツ、カットフルーツなど(調味料無添加)が含まれます。
魚介類では調理しやすいように切り分けられた切り身や刺身も、生であれば生鮮食品となり、スライス肉やひき肉も塩や醤油などで味付けされていない場合は、生鮮食品として扱われます。
| 生鮮食品の例 | 加工食品の例 | 判断のポイント | |
|---|---|---|---|
| 農産物 | ・丸ごとの野菜、果物 ・カット野菜、カットフルーツ ・精米、玄米 | ・漬物 ・ドレッシングがかかったサラダ ・乾燥野菜、冷凍野菜 ・ジャム | ・調味料の有無 ・加熱処理の有無 ・乾燥、冷凍加工の程度 |
| 水産物 | ・鮮魚(丸魚) ・刺身 ・切り身 ・生の海藻 | ・塩干魚(塩鮭など) ・しょうゆ漬けマグロ ・干物 ・魚の燻製品 ・缶詰 | ・塩蔵、干物加工 ・調味料の使用 ・加熱、燻製処理 |
| 畜産物 | ・精肉(切り身・挽肉) ・卵 | ・味付け肉 ・ハム、ソーセージ ・加熱済み肉製品 ・乳製品 | ・調味料の使用 ・加熱、発酵処理 ・加工度の高さ |
生鮮食品の特徴

生鮮食品の特徴は「鮮度」が最も重要です。自然の恵みを直接届ける魅力がある一方、品質管理の難しさや流通面での課題も存在します。
食品ロス削減や適切な流通体制構築は現代の食品業界の重要テーマです。生鮮食品の特性を理解しましょう。
| 品目例 | 冷蔵保存期間 | 冷凍保存期間 | 保存のポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 野菜類 | ・レタス ・キャベツ ・トマト ・きゅうり | ・3~5日 ・1~2週間 ・4~7日 ・3~5日 | ・不向き ・3ヶ月 ・2ヶ月 ・不向き | ・葉物は水分を保つように新聞紙などで包む ・根菜類は土を落とし、乾燥させてから保存 ・トマトなど一部は常温保存が適している場合も |
| 果物類 | ・りんご ・みかん ・バナナ ・いちご | ・2~4週間 ・1~2週間 ・3~5日 ・2~3日 | ・6ヶ月 ・3ヶ月 ・不向き ・1年 | ・多くの果物はエチレンガスを出すため、他の野菜と分ける ・バナナは常温保存が基本 ・いちごなどのベリー類は洗わずに保存 |
| 魚介類 | ・生魚(切り身) ・刺身 ・貝類 ・イカ・タコ | ・1~2日 ・当日~翌日 ・1~2日 ・1~2日 | ・2~3ヶ月 ・2週間 ・1ヶ月・1~2ヶ月 | ・購入後はすぐに冷蔵保存 ・できるだけ0℃に近い温度で保存 ・ラップで空気に触れないようにする ・内臓は早めに取り除く |
| 肉類 | ・牛肉 ・豚肉 ・鶏肉 ・ひき肉 | ・2~3日・1~2日 ・1~2日 ・当日 | ・1ヶ月 ・3週間 ・2週間 ・2~3週間 | ・小分けにして保存すると使いやすい ・空気に触れないようにラップで包む ・ドリップ(肉汁)が他の食品に触れないようにする |
| 卵・乳製品 | ・生卵 ・牛乳 | ・2~3週間 ・開封後3日 | ・不向き ・冷凍可(風味変化) | ・卵は冷蔵庫のドアポケットではなく本体に保存 ・牛乳は開封後はできるだけ早く消費 |
品質劣化が早く、温度管理が重要
生鮮食品は傷みやすいため、温度や湿度の管理が品質維持に不可欠となります。とくに、鮮魚や精肉の鮮度は冷蔵・冷凍技術や流通スピードによって大きく左右されるため、店頭での陳列や家庭の冷蔵庫においても、適切な温度帯を保つよう注意が必要です。
一般的な生鮮食品の適切な保存温度として、野菜・果物は種類により異なりますが、多くは5〜10℃で保存します。ただし、バナナやトマトなどは例外的に常温保存が適している場合もあります。魚介類は0〜2℃での保存が理想的で、氷温での保存が最も効果的です。精肉は0〜4℃での保存が適しています。
特に夏場は、買い物から帰宅までの間でも温度上昇による品質劣化が進むため、保冷バッグの使用や、生鮮食品を最後に買うなどの工夫も役立ちます。
季節や天候に左右されやすい
農産物や水産物は自然環境の影響を受けやすく、収穫量や漁獲量が不安定という特徴があります。自然条件により生産量が変動するため、市場や店頭での価格や品揃えにも大きな影響が及びます。
発生しうる状況として、天候不良時の価格高騰、豊作・豊漁時の値下がり、小売店の売り場構成への影響、飲食店メニューの季節変動などがあげられます。
生鮮食品の現象として、台風や長雨による野菜の不作、海水温の変化による漁獲量の減少などが見られます。一方で「旬」の時期には栄養価が高く、味も良い上に価格も比較的安定しており、食材を最も魅力的に楽しめる時期となっています。
需要の変動に対応しづらい
加工食品と違い、生鮮食品は生産から流通までの特性により、急な需要変動に即座に対応することが難しいのが現状です。
自然の営みに依存する生産サイクルは人為的に大きく短縮することができないため、市場の需要変化に柔軟に対応できないという課題があります。
対応が困難な理由として、生産に一定期間が必要(農産物の播種から収穫まで)、天候による生産量の制約、保存可能期間の限界などがあげられます。
こうした特性から、生鮮食品市場では需要急増時の品薄状態、生産過多による食品ロス、価格の不安定性といった問題が発生しやすく、安定供給には計画的な生産体制や輸入調整、そして消費者の理解と協力が重要です。
地域性と多様性
生鮮食品は地域の気候や風土に密接に関連しており、日本各地で特色ある産物が見られます。日本は南北に長く多様な気候を持つため、それぞれの地域環境に適した農作物や水産物が発達してきました。
地域特産品の例として、青森のりんご、高知のナス、静岡のみかん、北海道のじゃがいもなどがあげられます。
この地域ごとの特色ある生産は、日本の食文化を豊かにするだけでなく、多様な品種の保存や「地産地消」による環境負荷の低減など、さまざまな社会的・経済的メリットをもたらしています。
同じ野菜や果物でも地域ごとの品種改良や栽培方法の違いにより、日本の食の魅力が形成され、生鮮食品を通じて地域の特色を味わうことができます。
生鮮食品の表示ルール
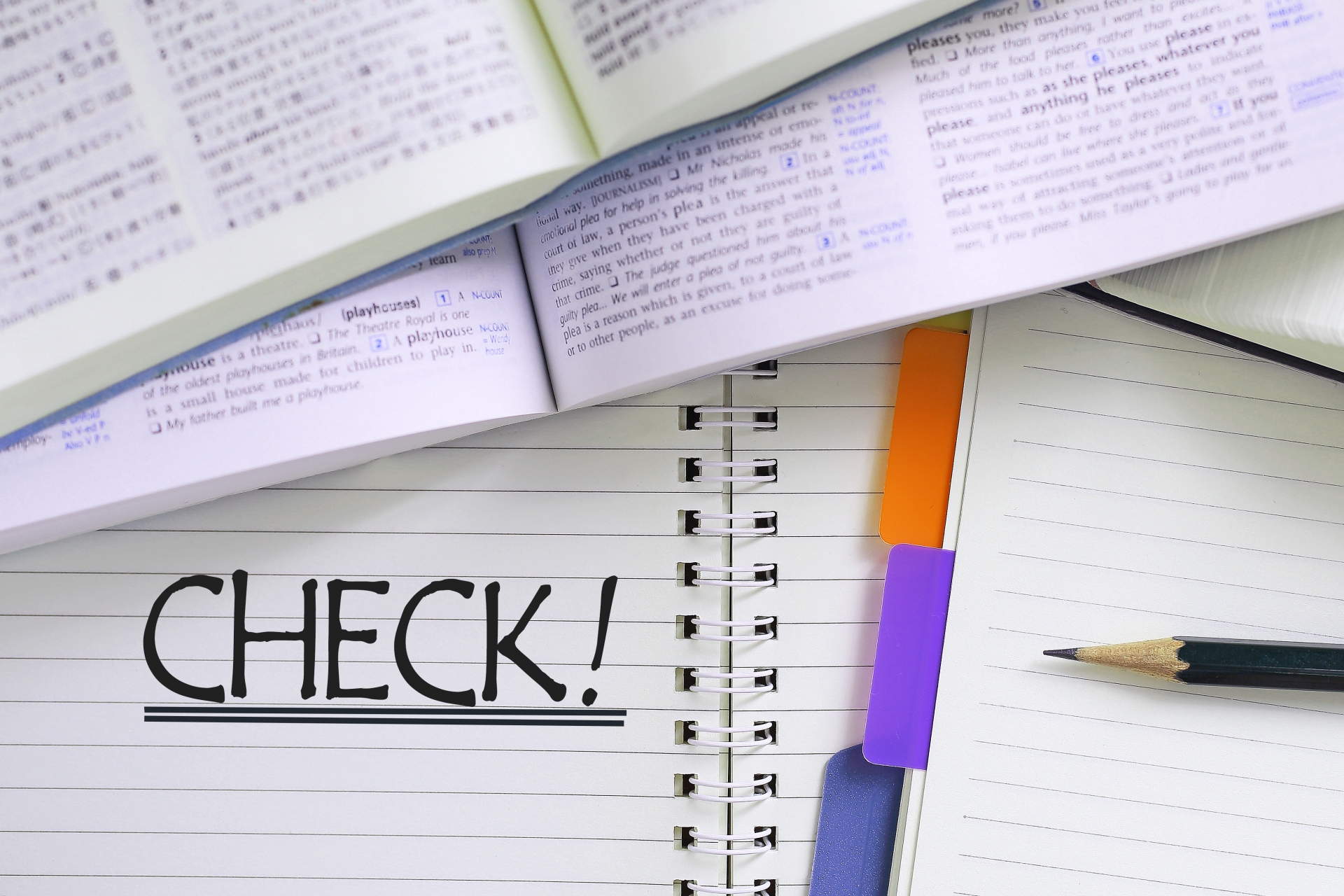
生鮮食品の表示は、消費者保護と信頼性確保のために法律で定められています。
名称と原産地表示の義務
食品表示基準では、生鮮食品に「名称(品名)」と「原産地」の表示が義務付けられています。消費者が産地や品目を正確に把握できるよう、具体的な表示が求められます。
【名称表示のルール】
- 農産物:「キャベツ」「りんご(ふじ)」など品目名
- 水産物:「まぐろ(本マグロ)」「さば」など魚種名
- 畜産物:「牛肉(肩ロース)」「豚肉(バラ)」など畜種名と部位名
【原産地表示のルール】
- 国産品:都道府県名または一般に知られている地名
- 輸入品:原産国名
- 魚介類:漁獲海域名(例:三陸沖、相模湾)の表示も可能
消費者の適切な選択に役立つよう、より具体的な産地表示が推奨されています。
業務用生鮮食品表示制度
平成20年4月から導入された制度により、生鮮食品は用途によって表示内容が異なります。
| 区分 | 定義 | 表示の特徴 |
|---|---|---|
| 業務用生鮮食品 | 加工食品の原材料となる生鮮食品 | 名称と原産地の表示は必須だが、一般消費者向けほど詳細な表示は不要 |
| 一般用生鮮食品 | 生鮮食品のまま一般消費者に販売されるもの | より詳細な表示が必要 |
業務用生鮮食品では、取引先に対して納品書や送り状などの書類による情報提供も認められています。
表示を見る際のポイント
生鮮食品を購入する際は、以下の点に注目すると安全で信頼できる食品選びにつながります。
確認すべきポイントとして、原産地では国内産か海外産か、地域による品質や価格差を確認し、名称では種類や部位、魚介類の漁獲海域などの詳細表示をチェックします。
また、加工の有無では味付けや添加物の有無を確認し、生鮮品か加工品かの判断材料とします。
表示内容に疑問がある場合は、販売員に確認するとよいでしょう。食品表示法に基づく適切な表示は、生産者と消費者の信頼関係を築く基盤となります。
遺伝子組換え表示ルール
一部の生鮮食品(主に大豆やとうもろこしなど)については、遺伝子組換えに関する表示ルールが適用されます。
遺伝子組換え表示の種類として、「遺伝子組換えである」は遺伝子組換え農産物が使用されていることを示し、「遺伝子組換え不分別」は遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていないことを表します。
「遺伝子組換えでない」は分別生産流通管理が行われている非遺伝子組換え農産物であることを意味します。
「遺伝子組換えでない」と表示するためには、生産・流通の全過程で非遺伝子組換え農産物であることが確認できる管理が行われていることが条件となります。
生鮮食品と加工食品の境目

スーパーでは、商品の分類に迷うことがよくあります。生鮮食品と加工食品の境界は、主に「調味や加熱の程度」によって決まります。
生鮮食品と加工食品の境界は、「素材の本質的な変化」で判断します。形状や鮮度を保つ最小限の加工は生鮮食品ですが、味や食感を大きく変える加工は加工食品となります。
| 分類 | 加工食品の例 | 生鮮食品の例 |
|---|---|---|
| 処理方法 | ・塩蔵、糖蔵、酢蔵などの処理 ・乾燥、燻製、油漬けなどの保存処理 ・調味料を加えての味付け ・加熱調理(炒める・茹でる・焼くなど) ・缶詰、瓶詰め、レトルト処理 | ・単純なカット、スライス、皮むき ・冷蔵、冷凍(品質保持目的) ・洗浄、トリミング(不要部分の除去) ・真空パック(鮮度保持目的) |
| 代表的な商品 | ・塩蔵、糖蔵、酢蔵などの処理 ・乾燥、燻製、油漬けなどの保存処理 ・調味料を加えての味付け・加熱調理(炒める、茹でる、焼くなど) ・缶詰、瓶詰め、レトルト処理 | ・カット野菜パック(生のままカット ・刺身パック(魚をスライスのみ) |
| 判断が難しい商品 | ・総菜、お弁当(味付けや加熱調理工程) ・味付け肉(調味料や下味を使用) | ・刺身の盛り合わせ(調味料なし) ・カット野菜ミックス(ドレッシングなし) |
購入時のチェックポイントとして、パッケージの表示をしっかり確認し、調理工程の有無を注意深く観察し、味付けや加熱の程度に着目することが重要です。
消費者は表示内容を十分に確認し、どのような加工がされているかを把握しましょう。表示ルールも異なるため、製造・販売側も消費者も、この区別を正しく理解する必要があります。
生鮮食品を取り扱う際の注意点

生鮮食品の安全性と品質を維持するには、適切な取り扱いが不可欠です。消費者と事業者それぞれの立場で、重要なポイントがあります。
消費者向けのポイント
生鮮食品の品質を保つためには、正しい選び方と保存方法が重要です。以下のポイントを押さえることで、より安全で美味しい食品を選び、保存することができます。
生鮮食品の品質を判断するには、目視と嗅覚による慎重な確認がポイントです。外見だけでなく、触感や香りを含めて総合的に評価し、鮮度の高い食品を選びましょう。
表示ラベルのチェック
原産地の確認、賞味期限・消費期限の把握、生産者や製造元の情報チェックが基本となります。食品選びの最初の指標となるのが、原産地や賞味期限・消費期限です。
これらの情報により、商品の背景を理解し、品質と安全性を事前に確認できます
温度管理のコツ
冷蔵庫の適温は3〜5℃に設定し、冷凍庫は開閉を最小限に抑え、食品の種類に応じた保存方法を選択することが大切です。
生鮮食品の鮮度と品質を保つためには、適切な温度管理が不可欠です。温度変化は食品の風味や栄養価に大きな影響を与えるため、細心の注意が必要です。
鮮度の見極め方
野菜・果物についてはみずみずしさ、色、艶感、弾力、茎の状態を確認し、魚介類では目の透明感、エラの色、身の弾力、生臭さの有無をチェックしましょう。
肉類については色、艶感、脂肪の状態、ドリップの具合を観察することが大切です。
業者向けのポイント
生鮮食品の品質維持には、流通段階での細心の注意が求められます。以下のポイントを押さえることで、安全で高品質な食品を提供できます。
流通スピードの確保
低温輸送の徹底、迅速な輸送と在庫管理、鮮度を最大限に保つ輸送方法の選択が必要です。生鮮食品の品質は、流通過程で大きく左右されます。
輸送中の温度管理と時間管理は、商品の価値を保つ上で最も重要な要素となります。
衛生管理と法令遵守
食品表示法の遵守、HACCPなどの衛生管理システムの導入、定期的な衛生状態の確認と改善を実施することが求められます。
食品の安全性を確保するためには、厳格な衛生管理と法令遵守が不可欠です。常に最新の衛生管理技術や法規制に対応し、消費者に信頼される食品を提供することが必要です。
在庫管理の工夫とロス削減
需要予測に基づく適切な発注、鮮度保持技術の活用、期限間近商品の戦略的な販売、加工品への転換、フードバンクへの寄付などの取り組みが効果的です。
適切な在庫管理は、食品ロスの削減と経営の効率化につながります。社会的責任と経済的合理性の両面から、これらの施策が重要な意味を持ちます。
まとめ

生鮮食品は、加工されていない状態で提供される農産物・水産物・畜産物を指し、私たちの食生活に欠かせない存在です。
その定義や特徴、表示ルール、加工食品との違い、保存や取り扱いの注意点までを整理しました。鮮度の管理や表示の見方を正しく理解することで、品質の高い商品を選びやすくなり、食品ロスの抑制にもつながります。
生鮮食品を扱う上で必要な知識を正しく身につけ、日々の選択や管理に役立てましょう。
生鮮業界に特化した求人を探すなら、「オイシルキャリア」がおすすめです。
業界経験者はもちろん、未経験者向けのサポートも充実。営業・事務・現場スタッフ・ドライバーなど、多彩な職種から自分に合った仕事が見つかります。
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /







