スーパーの売り場や求人情報などでよく目にする「青果(せいか)」という言葉。なんとなく野菜や果物を指すイメージはあるものの、その正確な意味や業界での使われ方については、意外と知られていません。
そこで今回は、「青果とは何か?」を改めて整理しながら、関連する用語や分類の違い、加工青果と生鮮青果の見分け方までわかりやすく解説します。
食品業界への就職・転職を考えている方や、青果流通に関心がある方はもちろん、日々の買い物で「これって野菜?果物?」と疑問を感じたことがある方にもおすすめの内容です。
「青果」の意味とは? スーパーや日常での使われ方

「青果売り場」や「青果店」など、私たちの生活にすっかり馴染んでいる言葉「青果」。この言葉にはどのような意味があり、どんな場面で使われているのでしょうか。まずは、野菜や果物との関係も含めて、基本的な定義を整理していきます。
「青果」とは、“野菜と果物の総称”
「青果(青果)」とは、野菜と果物を合わせた総称です。
日常的には、スーパーの「青果コーナー」や「青果売り場」、「青果店」といった言い方で使われており、葉物野菜や根菜、果物などの生鮮品を広く指す言葉として定着しています。
この「青果」という言葉は、家庭内の買い物シーンだけでなく、流通や小売、求人情報の中でも頻繁に用いられる業界用語でもあります。たとえば、「青果スタッフ」「青果部門」などは、野菜・果物の仕分けや陳列、販売などを担当する職種を指します。
なぜ「青果」とひとくくりにするの?
野菜と果物には明確な境界がない品目も多く、分類が難しい場合があります。たとえば、トマトやなす、きゅうりなどは植物学的には「果実」にあたりますが、食文化的には「野菜」として扱われています。
反対に、すいかやメロンは甘くて果物のように思われがちですが、「野菜的果実」として分類されることもあります。
このように、一部の作物がどちらとも言い切れない曖昧な存在であることから、実務上の呼び方として「野菜・果物」とあえて分けるのではなく、「青果」とまとめて表現するのが合理的とされています。

「青果」の語源とは?歴史から見る言葉のルーツ

「青果」という言葉には、長い歴史的背景があります。ここからは、野菜が「青物(あおもの)」と呼ばれていた時代から、「青果物」という言葉が制度的に使われるようになるまで、言葉の成り立ちと移り変わりをたどっていきましょう。
昔の野菜は「青物(あおもの)」と呼ばれていた
かつての日本では、野菜のことを「青物(あおもの)」と呼んでいました。これは、当時出回っていた野菜の多くが、ほうれん草やネギなどの葉物中心で、緑=青いもの=野菜というイメージが定着していたためです。
にんじんやかぼちゃのような色の濃い野菜も一部出回っていましたが、まだ品種改良や輸入が盛んではなく、全体として野菜のバリエーションは限られていました。そのため、「青物」という言葉で野菜全般を指すことに、さほど違和感がなかったと考えられます。
こうした背景から、江戸時代から明治期にかけては、野菜を扱う商人を「青物商(あおものあきんど)」、野菜を売買する場を「青物市場(あおものいちば)」と呼ぶのが一般的でした。
これらの呼称は、現在の青果市場や卸売市場の前身ともいえる存在であり、「青果」という言葉のルーツのひとつにもなっています。
「青果物」という言葉が登場したのは大正時代
このように、かつては「青物」と呼ばれていた青果ですが、実際に「青果」という言葉が広く使われるようになったのは、大正時代以降とされています。
野菜や果物の流通が拡大し、品目の種類も増えていく中で、従来の「青物」では表現しきれない状況が生まれたためです。
とくに、農業制度や市場流通の整備が進むにつれ、野菜と果実を一括して“商品”として取り扱う必要性が高まり、「青果物(せいかぶつ)」という言葉が実務上の用語として定着していきました。
その後、1971年に制定された卸売市場法(2020年には「卸売市場法の一部を改正する法律」が施行)では、「青果物」が正式に使用され、野菜および果実を含む農産物の分類として法的に明文化されています。
あわせて農林水産省の省令でも、市場の種別や品目分類において「青果物」という用語が用いられるようになり、現在に至っています。
📌 参考:農林水産省「卸売市場情報」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/index.html
加工青果と生鮮青果の違いとは?

「青果」とひとことで言っても、実際に売場に並ぶ商品にはさまざまなタイプがあります。
とくに、スーパーや業務用の現場では、そのままの形で販売される「生鮮青果」と、カットや下処理が施された「加工青果」とに大きく分けられます。
ここからは、それぞれの定義や見分け方を見ていきましょう。
「加工青果」と「生鮮青果」の意味と定義を整理
「生鮮青果」とは、収穫後にほとんど加工されることなく、丸ごとの状態で流通・販売される野菜や果物を指します。キャベツや大根、りんごやみかんなどが代表的で、店頭で見かける「丸のまま」の商品がこれにあたります。
一方の「加工青果」は、皮むき・カット・袋詰めなどの加工が施された青果を意味します。千切りキャベツ、カットフルーツ、サラダミックスなどがこれに該当し、調理の手間を省く目的で販売されることが多くなっています。
加工青果の多くは、専用の加工センターや工場、店舗内でのバックヤードなどで作業されており、業務用としてまとめて出荷されるケースもあります。流通過程や保存方法に違いがあるため、生鮮品とは別の管理基準で取り扱われることも一般的です。
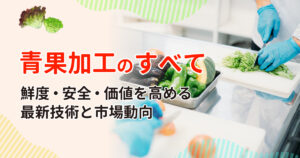
加工青果と生鮮青果を見分ける5つのポイント
スーパーなどで青果コーナーを見ていると、「これって加工品?それとも生のまま?」と迷うことがあるかもしれません。両者の違いを見分けるためのポイントは、主に以下の5つに整理できます。
- 包装の有無
生鮮青果は丸ごと・むき出しで並ぶことが多く、袋詰めでも未加工品が中心です。一方、加工青果はカット・皮むきなどの処理がされており、必ず包装されています。 - 日付表示
生鮮青果には賞味・消費期限の表示は基本ありませんが、加工青果は消費期限や加工日がパッケージに明記されています。 - 陳列場所
生鮮青果は常温または涼しい場所に、加工青果は冷蔵棚に並べられていることが一般的です。 - 値段と量
加工青果は少量で割高になる傾向があり、ミックス野菜など利便性重視の商品が多く見られます。 - 表示内容
加工青果には「そのまま使える」「洗わずOK」などの手軽さを強調した表示が多く、生鮮青果では「産地」「旬」など素材の魅力をアピールしたPOPが中心です。
このように、包装・表示・陳列などを見れば、どちらのタイプかはすぐに見分けがつきます。現場での判断はもちろん、食品業界を志す方にとっても基本的な視点となるでしょう。
まとめ
「青果」とは、野菜と果物をあわせて指す総称であり、日常生活から流通現場まで幅広く使われている言葉です。
もともとは「青物」と呼ばれていた野菜が主流だった時代背景から生まれ、時代とともに「青果」「青果物」として制度的にも定着してきました。
また、現在の売場では、丸ごとの状態で販売される生鮮青果と、あらかじめカットや包装がされた加工青果があり、パッケージや表示、陳列方法などから見分けることができます。
こうした基礎知識を知っておくと、買い物での選び方に役立つのはもちろん、青果部門や流通業界への就職・転職を考える際にも強みになります。
身近な「青果」という言葉の背景を理解することで、日常もキャリアもより広い視点でとらえられるはずです。
\📢 生鮮業界への転職なら【オイシルキャリア】/
🌱 オイシルキャリアでは、青果をはじめとした食品業界の求人を多数掲載中! 専門のアドバイザーがあなたの転職をサポートいたします。
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /





の意味と使われ方とは?-昔の「青物」からスーパーの売場まで.png)

