青果の流通を支える「卸売市場」。その名前は聞いたことがあっても、実際にどのような仕組みで動き、どのような人たちが関わっているのかまで理解している人は意外と少ないかもしれません。
とくに近年では、制度の変化や流通の再編に加え、入荷や価格の情報をデジタルで管理する仕組みや、取引のオンライン化など、IT化による大きな変化も見られます。
そこで今回は、青果卸売市場の基本構造から取引のルール、関係者の役割、最新の流通トレンドまでを網羅的に解説。
青果市場について知りたい方や、仕入れや販売に関わる実務担当者の方に向けて、「制度を知り、戦略に活かす」ための知識を整理してお届けします。
青果の卸売市場とは?〜役割と仕組み〜

青果物が日々安定して供給される裏側には、全国に広がる「卸売市場」の存在があります。この市場は単なる “売り場”ではなく、流通全体の要所として、集荷・分荷・価格決定といった重要な役割を担っています。
まずは、青果卸売市場がどのような機能を持ち、どんな構造で成り立っているのかを押さえていきましょう。
青果の流通を支える「卸売市場」4つの役割
青果の流通は、生産者である農家から始まり、卸売市場を経て、仲卸業者や小売業者、そして最終的に消費者へと届きます。
この一連の流れの中で、卸売市場は“つなぎ役”として中心的な役割を担っており、主に次の4つの機能を果たしています。
まず、生産地から集めた青果物を広く販売する「卸売」。次に、全国の産地から商品を集める「集荷」、それを買い手ごとに仕分ける「分荷」があります。
そして、セリや相対取引によって価格を決める「価格決定」も重要な機能です。ここで需給バランスを反映した“市場価格”が形成されます。
卸売市場内では、大卸や仲卸といった卸売業者が取引を担い、仕入れた商品を適切な数量と価格で販売先に振り分けていきます。
このように、卸売市場の機能が連動することで、青果の安定供給と効率的な流通、価格の形成が実現し、日々の食卓に安定した品質の商品が届けられているのです。

「公設市場」と「私設市場」の違いとは?
卸売市場は「公設」と「私設」に分かれ、それぞれ運営主体や制度に違いがあります。
公設市場は、都道府県や市区町村といった自治体が運営する制度型の市場で、取引ルールや施設の基準が法律で厳密に定められています。
全国の産地から青果物が集まりやすく、取引の透明性や公正さが確保されているのが特徴です。
一方の私設市場は、民間企業などが開設・運営する市場で、公設市場に比べて自由度が高く、柔軟な運営が可能です。
地域の農家や小規模な事業者との距離が近く、顔の見える関係性のなかで取引が行われるなど、地元に密着した流通を支える役割を担っています。
どちらの市場も法制度に基づいて設置されていますが、以下のように目的に合わせて使い分けがされています。
📌 公設市場と私設市場の使い分け方
- 全国規模の流通や価格の公平性を重視する場合
→ 公設市場 - 地域に根ざした柔軟な取引や、顔の見える関係性を重視する場合
→ 私設市場
卸売市場の種類と役割とは?「中央」と「地方」の違い

全国に点在する卸売市場には、公設・私設のほかに「中央卸売市場」と「地方卸売市場」という2つの大きな分類があります。
どちらも青果物流の中核を担う存在ですが、制度や運営体制、取引スタイルに違いがあり、それぞれに向き不向きがあります。
ここからは、中央と地方それぞれの市場が持つ特徴を整理し、出荷先や仕入れ先としてどのように使い分けるべきかを考えていきましょう。
制度面とスケール感で選ぶなら「中央卸売市場」
中央卸売市場は、公設市場の中でもとくに制度面が整った流通の中核拠点です。国の認可を受けて開設されるこの市場は、取引の公正さや透明性に優れ、流通の安定を支える仕組みが整っています。
たとえば、豊洲市場(東京都)や大阪市中央卸売市場など、全国に設置された拠点は、規模・取扱量ともにトップクラス。全国各地から青果物が集まり、広域な流通ネットワークが形成されています。
また、取引の制度化と運営の厳格さも大きな特徴です。市場内では、登録制の卸売業者・仲卸業者が中心となり、セリをはじめとする取引が明確なルールに基づいて行われます。記録や搬出入の管理も徹底されているので、事業者間の信頼性も充分です。
さらに、青果物の品揃えが豊富で、量の確保がしやすいことも大きな魅力。大量仕入れや多店舗展開を行う企業にとっては、必要な商品を安定して調達できる心強い仕入れ先となるでしょう。
「公平性」「規模感」「信頼性」。こうした要素を重視するなら、中央卸売市場は欠かせない選択肢といえます。
地域性や柔軟性を重視するなら「地方卸売市場・私設市場」
中央卸売市場に対し、地方卸売市場や私設市場はより地域に根ざした存在です。
地方市場は自治体が設置する点では中央と同じですが、対象地域は限定的。規模は小さくても、地元の流通を支える役割を担っています。
一方、私設市場は、民間企業や農協、生協などが運営する市場です。国の許可ではなく、都道府県の認可で設置されており、取引のルールや運営方針には一定の自由度があります。
こうした市場では、地場産品の扱いが多く、地元スーパーや飲食店などのニーズにきめ細かく対応可能。取引の形式も柔軟で、顔の見える関係性を重視した取引が行われることも少なくありません。
「小回りが利く」「地域との距離が近い」「柔軟な取引ができる」。これらは地方市場・私設市場ならではの魅力です。規模よりもスピード感や柔軟性を重視したい事業者にとって、有力な選択肢となっています。
出荷・仕入れの目的に応じて市場を使い分ける
では、さまざまな種類の市場は、どのように選べばよいのでしょうか。
青果を「仕入れる側」と「出荷する側」とでは、それぞれの立場によって重視すべきポイントが異なるため、市場の選び方も変わってきます。
仕入れる側(小売業者・飲食店など)の選び方
- 広域配送・大量仕入れを重視する場合
中央卸売市場がおすすめ。品揃えが豊富で、安定した物流と取引体制が整っている。 - 地場産品・柔軟な対応を重視する場合
地方市場や私設市場が適している。担当者との距離も近く、取引もスピーディー。 - 店舗の規模や販売スタイルに応じて選ぶ
チェーン店なら中央、個人経営なら地方や私設市場が動きやすい。
出荷する側(生産者・集荷業者など)の選び方
- 販路を広げたい・高品質な商品を広く展開したい場合
中央卸売市場へ出荷が◎ 全国対応で集客力・販売力がある。 - 小ロット出荷・地元密着の販売を希望する場合
地方市場や私設市場へ出荷が◎ 柔軟な契約や取引スタイルが可能。
取扱商品や販売スタイル、規模感、距離感など、重要なのは「どこが一番便利か」ではなく、「どこが自社の事業に合っているか」という点です。
中央・地方・私設、それぞれの特長を理解し、自社に合った市場との関係を築くことが、長く安定した取引につながります。
青果市場での取引の流れは?セリと相対、価格の決まり方
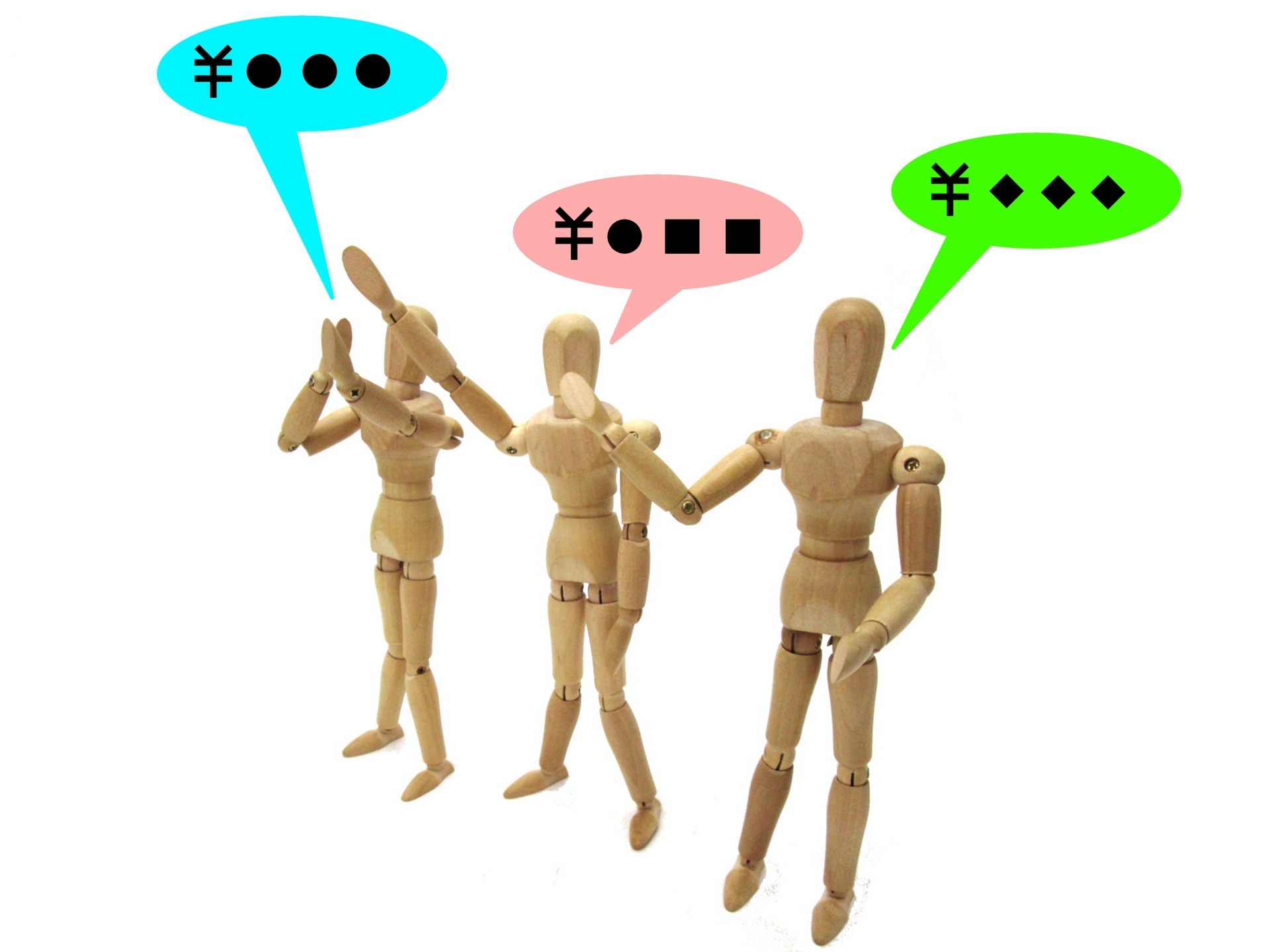
ここからは、市場で行われている取引の方法や価格の決まり方について見ていきましょう。
青果卸売市場における代表的な取引方法には、「セリ」と「相対(あいたい)取引」の2つがあります。
市場のイメージとしてはセリが強く想起されがちですが、現在は、実際の現場では柔軟に対応できる「相対取引」が主流。中央卸売市場では、全体の8〜9割を占めることもあります。
両者の違いを理解して上手に選択できるかどうか。これが、青果ビジネスの利益に大きく影響するのです。
「セリ取引」はスピード勝負の “公開オークション型”
セリは、青果卸売市場を象徴する取引手法のひとつです。
決められた時間に、集荷された野菜や果物を公開の場で販売し、買参人や仲卸がその場で価格を提示。最も高い値をつけた人が落札するというオークション形式で、販売の公平性と透明性が確保される方法です。
セリは通常、早朝に一斉にスタートし、テンポよく進行します。
ひとつの商品につき、数秒から十数秒で価格が決まり、次の商品へと移るため、買い手には商品知識や品質の目利き、そして相場観に基づいた素早い決断力が必須です。
このように、時間との勝負であるセリ取引では、競争原理が働く点も大きなポイント。
とくに旬の品目や品質の良い商品は、複数の買い手が積極的に入札するため、高値がつくことも少なくありません。
これは、生産者側にとっても価格面でのチャンスとなりやすく、「良いものを作ればきちんと評価される」というインセンティブの役割も果たしています。
「相対取引」は数量・納期・仕様まで調整できる “すり合わせ型”
相対取引は、売り手と買い手が個別に交渉して価格や数量を決める方法です。
セリのような一斉競売とは異なり、じっくり話し合いながら条件を調整できるので、相場変動にも左右されにくく、比較的安定した取引が可能です。
たとえば、「Lサイズのりんごを箱単位で揃えてほしい」「週末に合わせて配送してほしい」など、現場の状況や顧客の都合に応じて細かい調整がしやすく、実際の販売現場とつながった仕入れが可能になります。
継続的な取引関係が築きやすく、相手の事情を加味した “融通の利く商談”ができるのも相対取引ならでは。現在では、多くの市場で取引の主流となっています。
一方で、価格の透明性はセリほど高くないため、良くも悪くも、相場観や交渉力が取引結果に直結する面もあります。
⚖️ セリと相対の使い分けポイント
セリと相対は、目的や状況に応じて使い分けるのが一般的です。
- スピードと公平性を重視するなら → セリ
- 柔軟性や継続性を重視するなら → 相対取引
価格はどう決まる? 影響するのは、需給バランスと流通コスト
青果市場での価格(=相場)は、その日の入荷量や需要の動き、天候などの自然条件によって日々変動します。
たとえば、好天により一気に出荷量が増えれば価格は下がり、逆に不作による供給減少があれば高騰する、といった具合です。
これに加え、クリスマスやお正月などの季節イベントや消費者の関心、輸送コストや為替レートといった流通環境の変化も相場に反映されます。
つまり相場とは、「いま何が、どれだけ出回り、どのくらい求められているか」を映し出す数値です。
日々の価格変動には、需給の動きや自然条件、流通環境などが反映されており、市場の状況を知るうえで欠かせない指標となっています。
市場で仕入れるには? 買参人制度のしくみと手続きの流れ

卸売市場で青果物を仕入れるには、「買参人(ばいさんにん)」としての登録が必要です。
買参人とは、市場のセリや相対取引に参加し、卸売業者・仲卸業者から商品を直接仕入れられる立場のこと。スーパーや八百屋、飲食店など、青果を扱う多くの業者がこの資格を取得しています。
ここでは、「誰が買参人になれるのか?」「登録にはどんな手続きがあるのか?」「そもそも登録するとどんなメリットがあるのか?」といった実務に直結する基礎知識を整理していきましょう。
誰でも参加できるわけではない! 買参人になるための条件とメリット
買参人の登録には一定の条件があります。
市場や自治体によって詳細は異なりますが、以下のような基準が設けられているのが一般的です。
- 青果物の販売や加工など、関連する事業を行っていること
- 営業実態があり、継続性のある法人または個人事業主であること
- 一定の資金力・信用があること(過去の債務履歴なども確認される)
- 市場の規則・ルールを遵守する意思があること
買参人として登録されると、市場で集まった多様な青果物を、タイムリーかつ競争力のある価格で仕入れることが可能になります。
とくに仲卸を通さずに直接仕入れができる点や、産地・品目の情報がリアルタイムで入る点は大きなメリットです。
また、継続して市場を利用することで、取引先との信頼関係も築きやすくなり、数量や価格の相談など、柔軟な交渉にもつながりやすくなります。
日々の仕入れを安定させ、事業を拡大していくうえで、買参人登録は心強い武器になると言えるでしょう。
【登録・更新の方法と注意点】事前準備でスムーズに手続きを!
買参人になるには、各市場または管轄自治体に対して登録申請を行う必要があります。手続きの流れは市場によって若干異なりますが、基本的には以下のステップで進められます。
✒️ 登録までの主な流れ
- 必要書類の提出(事業概要、登記簿、納税証明、身分証など)
- 資格・信用審査(営業実態や財務状況の確認)
- 面談や説明会への参加(市場によっては実施)
- 許可証の交付(登録完了)
登録後も、定期的に有効期限の更新が必要です。更新には再度書類の提出や審査が必要ですが、提出内容に不備があると審査に時間がかかることも。問い合わせは早めにし、余裕を持って進めることが重要です。
買参人制度、今後はどうなる?
買参人制度は、かつては「登録者のみが市場で取引可能」という閉鎖的な側面もありましたが、近年は見直しの動きが進んでいます。
たとえば、
- 一部市場では小規模事業者やフリーランスバイヤーも参入可能に
- インターネット経由での事前申込・購入制度の導入
- 民間流通網との接点拡大
といった変化が現れ始めており、「より多くの事業者が参加できる開かれた市場」へとシフトしつつあります。
こうした流れに対応するには、制度変更の情報をキャッチアップし、柔軟に仕入れ体制を整えておくのがカギ。取引機会の拡大はもちろん、デジタル化や民間参入が進めば、取引条件の幅も広がるでしょう。
まとめ
青果卸売市場は、単なる取引の場ではなく、流通全体を支える“基盤”そのもの。集荷・分荷・価格決定といった基本機能に加え、中央・地方・私設といった多様な市場形態、セリと相対による柔軟な取引手法、そして制度的な参加条件など、知れば知るほど戦略の幅が広がる世界です。
さらに近年では、市場を取り巻く環境も大きく変化。民間参入や制度の自由化、DXによる効率化の波、そして現場からの情報発信が相場や販売戦略に影響を与える時代が到来しています。
こうした背景を理解しておくことは、単なる知識ではなく、仕入れや販売の精度を高め、変化に強い青果ビジネスを構築するための“武器”になります。関連記事『青果市場の“次なる常識”をつかむ!データ活用・SNS発信・再整備の最前線』もぜひチェックしてみてください。
\📢「オイシルキャリア」では、青果の仕入れ・営業・流通に関わる正社員求人を多数掲載中!/
🌱 実務に活かせる知識をもとに、自分に合った職場を見つけたい方は、ぜひ一度チェックしてみてください。







