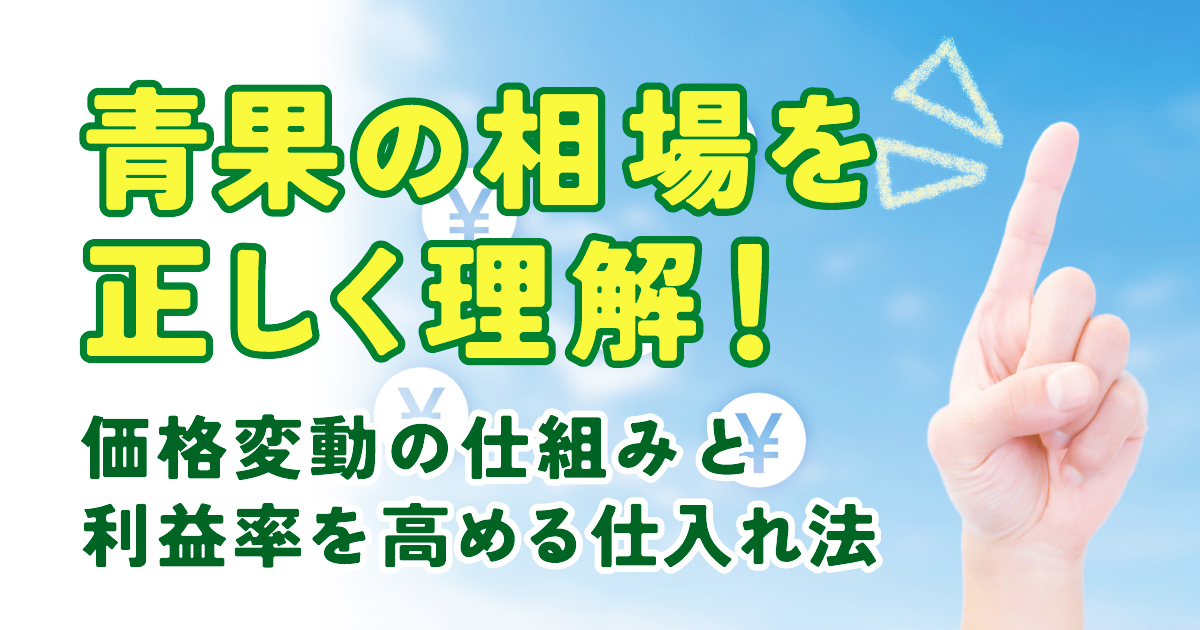青果の値段は、同じトマトでも日によって上下します。天気や収穫量、連休や行事、テレビでの話題化などなど、さまざまな出来事が重なって「その日のだいたいの値段(=相場)」が決まるからです。
本記事では、「相場とは何か」「なぜ変わるのか」を整理し、市場のしくみや価格が動きやすいタイミング、公開されている市況情報の読み方までを幅広くご紹介。さらに、相場の変動要因や市況データのチェック方法、便利な確認サイトなどもまとめています。
相場はどう決まる? 青果価格が日々変動する仕組みとは

飲食店や小売店で青果の仕入れを担当する方にとって、「相場とは何か」「なぜ価格が毎日変わるのか」といった基本を押さえることは、青果の流通を理解するうえでの土台になります。
まずは、青果相場の意味と、価格がどのように決まっているのかを段階的に整理していきましょう。
「相場」は市場で決まるその日の “基準価格”
青果における「相場」とは、その日に市場でやり取りされる取引価格の基準を指します。
たとえば、ある野菜が1箱2,000円で売買されていれば、それがその日の「相場」とされます。
一方で、相場は入荷量や需要、天候、行事などによって日々変動するため、完全に固定された価格ではありません。
青果の相場は「卸売市場」で決まる
青果の相場は、全国の卸売市場での取引を通じて形成されます。
出荷者(産地・JAなど)から集まった青果物が、市場に集荷され、買参人(仲卸・小売店・飲食店など)とのあいだで実際に取引されることで、その日の相場が決まります。
卸売市場は、公正で透明性のある取引を行うための場として制度的に整備されており、全国の主要市場では毎朝、一定のルールに基づいた取引が行われています。
こうした市場での売買は、青果の価格を「見えるかたち」で決定する仕組みになっており、その価格が全国の流通や販売現場でも参考にされています。
青果の価格は「セリ」と「相対取引」で決まる
卸売市場で青果の価格を決める方法には、「セリ」と「相対取引(あいたいとりひき)」の2つがあります。
セリは、出荷された青果物を競りにかけて、最も高い価格を提示した買参人に販売する方法です。
短時間で価格が決まり、入荷量が多い品目や鮮度の高い商品に用いられることが多くなっています。
📌【セリ】
◯ 複数の買参人による公開競争形式
◯ 公正性が高く、価格が透明
◯ 大量入荷品や鮮度重視の商品に多い
一方の相対取引は、売り手と買い手があらかじめ価格や数量を交渉し、合意の上で取引を成立させる方法です。
過去の取引実績や信頼関係に基づくケースが多く、現在では青果物の取引の大半が相対取引によって行われています。
📌【相対取引】
◯ 売り手と買い手のあいだで価格・数量を事前合意
◯ 柔軟な交渉が可能
◯ 過去の実績や信頼関係が重視される
どちらの方式も、市場内での需要と供給の状況を反映して価格が決まるため、日々の相場の形成に直接関わっています。以下の記事で詳細について解説しています。

価格はなぜ変動する? 青果の相場に影響する5つの要因

青果の相場は、市場内での取引によって決まりますが、その前提には日々変化するさまざまな外部要因があります。天候や災害、物流の影響、さらには行事や消費者の動向など…… 価格に影響を与える要素は一つではありません。
ここからは、青果相場を動かす5つの代表的な要因について、具体例を交えながら整理していきます。
① 天候や災害による作柄の変化
青果の価格に最も直接的な影響を与えるのが、天候や災害による作柄の変化です。
たとえば長雨や猛暑、台風などの異常気象が続くと、農作物の生育が悪化し、収穫量が減少します。これにより市場への入荷量が減り、品薄となった商品は相場が高騰しやすくなります。
葉物野菜のように1週間の天気で価格が大きく動く品目もあります。
⬆️【高騰しやすい青果】⬆️
◯ 葉物野菜(ほうれん草・小松菜・レタスなど):気温や日照不足の影響を受けやすい
◯ なす・ピーマンなどの果菜類:高温障害や風雨で傷みやすい
◯ イチゴなどの果物:天候次第で収量が大きく変動する
反対に、天候に恵まれた年には収穫量が増え、供給が潤沢になることで相場が下がるケースもあります。この場合、取引量自体は多くても、供給過多によって値崩れが起こりやすい傾向があります。
⬇️【下落しやすい青果】⬇️
◯ トマト・キュウリ:気温上昇で一気に収穫量が増えやすく、値崩れにつながる
◯ スイートコーン:一斉出荷で需給バランスが崩れやすい
◯ 夏場の枝豆やかぼちゃ:豊作時に過剰在庫化しやすい
こうした「不作」や「豊作」は、単なる天気の良し悪しではなく、地域ごとの気象条件や生産者の出荷判断にも左右されるため、価格予測が難しい要因のひとつとなっています。
② 需給バランス・輸送状況・為替などの経済要因
青果の相場は、農作物そのものの生育状況だけでなく、経済的な要因によっても大きく変動します。その中でも代表的なのが「需給バランス」です。特定の品目に人気が集中すれば価格は上がり、売れ行きが鈍れば相場は下がります。
また、輸送コストによる影響も少なくありません。
燃料費の高騰や人手不足などにより、物流の負担が増すと、輸送にかかるコストが価格に転嫁されやすくなるからです。離島や遠隔地への出荷が多い品目では、とくにその影響が大きくなります。
さらに、為替相場も無関係ではありません。
輸入に頼る品目では、円安によって仕入れ価格が上がり、国産品にも価格転嫁されることがあります。
とくに、バナナやオレンジなどの輸入果物をはじめ、近年ではブロッコリーやアスパラガスなどでも海外調達が一般化しており、為替の影響を受けやすい構造となっています。
③ 季節・行事・連休前後の特需
青果相場は、暦の動きにも大きく影響を受けます。とくに季節の変わり目や行事の前後には、特定の品目に対する需要が一時的に高まり、相場が上昇する傾向があります。
たとえば春の「ひなまつり」では菜の花やいちご、秋の「お彼岸」には里いもやれんこん、年末年始には大根やにんじん、みかんなどの需要が集中します。
これらの時期には、仕入れ量を増やす小売や飲食店が多く、価格が一時的に高騰しやすくなるのです。
また、大型連休やお盆、年末年始などの休日前には、業者のまとめ買いが増えるため、出荷量があっても相場が上がるケースもあります。反対に、連休明けや需要の谷間では一転して価格が下がることもあります。
④ 政策や制度変更による市場への影響
青果相場には、行政や制度の変化が影響することもあります。
たとえば農業政策の転換によって補助金制度が見直されたり、生産奨励品目が変更された場合、生産量や出荷意欲に変化が生じ、結果として相場に波が立つことがあります。
また、輸入品目に関わる規制緩和や関税の変更も、価格に大きく影響します。
たとえば輸入ブロッコリーの関税が下がれば、国産品との価格競争が強まり、相場が抑えられる可能性があります。逆に、検疫強化や輸入停止措置が取られると、代替品として国産の価格が高騰することもあります。
このように、制度や政策の動きは表面的には見えにくいものの、生産や流通の現場にじわじわと影響を与え、相場に変化をもたらす背景要因となっています。
⑤ 報道やSNSによる消費者心理の変化
青果の相場は、消費者の動向によっても左右されます。
とくに近年では、テレビやSNSで特定の野菜や果物が紹介されることで、突発的に需要が高まるケースが増えています。
たとえば、健康効果やダイエットに関する情報が広まったことで、アボカドやブロッコリーが一時的に品薄になり、価格が上昇した例もあります。
また、テレビ番組やレシピサイトで「使いやすい食材」として取り上げられた野菜が、数日間だけ相場を大きく動かすことも珍しくありません。
これらは、生産や流通の事情ではなく、「買いたい」という心理の変化によって引き起こされるのが特徴です。
一方で、風評被害や誤った情報が拡散された場合には、消費が急激に落ち込み、相場が大きく下がることもあります。
実際に、過去には農薬の誤報や放射線関連の報道によって、実際には安全性に問題がないにもかかわらず、商品の価格が暴落した例も見られました。
情報の拡散スピードが早まった今、報道やSNSによる消費者心理の変化は、相場を動かす “新しい要因”のひとつとして注目されています。
青果相場を知るための市況情報と価格表の基本

青果の相場は毎日変動するため、仕入れや販売の判断に活かすには、「どこで何が見られるのか」「どの情報に注目すべきか」といった最新の価格情報を継続的に把握しておくことが欠かせません。
ここからは、相場の水準や動向を知るうえで重要な「市況情報」「入荷予定」「卸売価格表」について見ていきましょう。
相場の流れと需給の傾向をつかむ!「市況情報」と「入荷予定」の見方
青果の相場を把握するうえで、まず注目されているのが、市場が毎日発信している「市況情報」と「入荷予定」です。
市況情報には、主要な青果物の品目別に、その日の取引価格(高値・中値・安値)や取引量などが掲載されており、現在の相場水準を知る手がかりになります。
📌【市況情報】
◯ 高値・中値・安値の記載があるため、相場の幅がわかる
◯ 入荷量と価格の相関を読み取ることができる
◯ 前日や前週との比較ができ、傾向を把握しやすい
◯ 品目別の動向が一覧で見られるため、売れ筋や相場変動の兆しをつかみやすい
あわせて確認されているのが「入荷予定数量」です。
入荷が多い日は供給が増えるため、相場が下がりやすくなり、逆に入荷が少ない日は価格が高騰する可能性があります。
とくに週明けや連休明けなど、物流のタイミングと重なる日は入荷量の変化が大きくなる傾向があります。
📌【入荷予定数量】
◯ 前日比で増減がわかる形式が多く、仕入れ判断に活用できる
◯ 中央市場の荷受会社(例:東京青果、大阪本場など)のサイトからも確認可能
◯ 週明けや連休明けなど特定日の変動に備える参考になる
これらの情報は、多くの中央卸売市場のウェブサイトで無料公開されており、「市況情報(今日)」「週間市況」「月間市況」といった形で期間別に閲覧できます。グラフ表示やCSV形式でのダウンロードに対応しているサイトもあり、前日や前週との比較も可能です。
仕入れ判断の材料に!「卸売価格表」の見方
市場が発信する市況情報の中には、「卸売価格表」という形式で提供されるデータもあります。
これは、青果ごとの当日の取引価格や入荷量などが一覧でまとめられているもので、仕入れ判断に直結する重要な資料となっています。
卸売価格表には、次のような項目が並びます。
【卸売価格表に記載される主な項目】
◯ 品目名・産地・等階級(秀・優など)
◯ 入荷数量(kgまたはケース数)
◯ 単価(高値・中値・安値)
◯ 前日比(価格や数量の増減)
とくに注目されているのは、「等階級」と「価格帯」です。
たとえば、同じトマトでも「秀品」と「優品」では価格が大きく異なりますし、産地によっても相場のベースが変わります。
また、価格は「1kgあたり」や「1ケースあたり」など、市場によって表記単位が異なります。さらに、品目が細かく分類されている場合もあり、「中玉トマト」「ミディトマト」などに分かれて掲載されることがあります。
※ なお、価格表は市場での取引をまとめたもので、実際の仕入れ価格は仲卸や買参人との交渉によって変わる場合があります。そのため、価格表は相場の目安として扱われています。
市況情報や相場を調べられる代表的なサイト5選

日々変動する青果の相場は、スマートフォンやPCから公開情報を確認することで把握できます。
市況情報だけでなく、産地の状況や天候、物流の動きまで掲載しているサイトもあり、相場を理解するうえで参考になります。
信頼性の高い統計データを提供する公的機関サイト。全国の市場動向を客観的に把握できます。
👉 農林水産省「毎日の卸売価格」
・全国の主要市場における青果物の「卸売価格」や「取扱数量」を統計的に確認できる
・日次・月次・年次など複数スパンの価格推移データが整備されている
・「野菜」「果実」など分類ごとの品目データをCSV形式でダウンロード可能
情報の更新頻度が高く、実務の現場でもよく参照されているサイトです。
・東京都内の各市場(大田・豊洲・淀橋など)の市況情報を一元的に確認できる
・野菜・果実・花きなど品目ごとに「当日分」「週間・月間」「入荷予定数量」などが揃っている
・CSV形式でのデータダウンロードが可能なページもあり、加工・比較にも使いやすい
豊洲市場を代表する荷受会社による市況情報。現場の相場感をリアルタイムに把握できます。
・当日の高値・中値・安値、入荷量、前年同日比などを一覧表示
・PDF/HTML形式で品目別に市況を閲覧可能
・週間・月間の市況や入荷予定数量も確認でき、現場の判断材料として有用
比較的シンプルな構成で、目的の情報に素早くアクセスできるサイトです。
・大阪市の中央卸売市場(本場・東部・南港)で扱われる青果・水産物・花きの市況情報を一元的に掲載
・「当日分」や「週間情報」「入荷予定数量」などをPDFで提供
・市場別・品目別に分類されており、西日本の取引動向を把握しやすい
愛知県内の青果市場に特化した信頼性の高い情報源で、出荷者・販売者の双方に役立ちます。
・名古屋・豊橋・岡崎など県内各市場の青果市況をPDF形式で週ごとに公開
・品目別の価格・出荷量に加え、「売れ筋」「販売苦戦品目」など実務的なコメントも掲載
・特定品目のトレンド把握や現場感のある分析が可能で、地域密着型の実用性が高い
なお、青果の相場は天候の影響を強く受けるため、天気アプリや農業向けの気象サービスも併用されています。価格情報とあわせて天候の動きにも注意を払うことで、より的確な仕入れ判断が行われています。
相場情報はどのように活用されている? 仕入れ・販売への活かし方とは
青果の仕入れや販売では、「いまの価格」だけでなく、「価格がどう変わってきたか」「これからどうなりそうか」といった相場の流れを読むことが欠かせません。
最後は、市況情報が仕入れや価格設定の場面でどのように使われているのかを見ていきましょう。実際にどのように活用されているのかを整理することで、相場と販売現場との関わり方がわかります。
使われ方1:仕入れのタイミングを考えるとき
青果の相場は日々変動するため、単日の価格だけでは全体の動きをとらえにくい面があります。数日から数週間の推移をあわせて見ることで、「上昇傾向か」「下落傾向か」といった流れがより明確になります。
たとえば、例年に比べて早い段階で高騰している場合、「今買っておかないとさらに上がるのではないか」という見方が挙がることがあります。逆に急落している最中であれば「あと数日待てば底値を狙える」と見極められることがあります。
仕入れのタイミングを誤ると、通常より高値で仕入れてしまい、販売価格を据え置いた場合は利益がほとんど出ない、あるいは赤字になるリスクがあります。
逆に、相場が落ち着くのを待てば、同じ数量でも仕入れ原価を抑えられ、粗利率を5〜10%改善できることもあります。相場は「点」ではなく「線」として捉えられることが多く、価格の推移を継続的に見ることが重要とされています。
使われ方2:仕入れ数量を決めるとき
仕入れる量の判断には、相場だけでなく入荷予定や市況全体の動きも関わります。たとえば、天候不良や産地の切り替わりなどで入荷数量が減る見込みがある場合、価格が上がる前に早めの確保に動くケースがあります。
一方で、豊作による価格下落が予測される場合には、仕入れを控えて様子を見ることで在庫リスクを避ける動きが見られます。とくに相場が乱高下しやすい品目では、数量の調整が損益に直結します。
相場の変動だけでなく、「どれくらいの量が出回るのか」「需要はあるのか」といった要素とあわせて確認されるのが一般的です。
使われ方3:販売価格を設定するとき
販売価格は、仕入れコストと市場価格のバランスを見ながら決められます。仕入れコストが上がっている時期に無理に安売りをすると赤字リスクが高まり、その一方で、価格をそのまま転嫁すると売れ行きが鈍ることもあります。
過去の相場推移や現在の市況を踏まえ、「相場に見合った価格」と「顧客の許容範囲」のバランスをとる形で価格設定が行われることが一般的です。
また、特売や値引きのタイミングを相場の動きに合わせて調整する例もあり、販売促進と収益維持の両立を図る手段とされています。価格は単に「仕入れ価格の何倍」という決め方ではなく、「今の市況で売れる価格帯」として意識される傾向があります。
ただし相場の急変は避けられないため、在庫量の調整や販促策を柔軟に組み合わせ、売れ残りリスクを抑える工夫も見られます。変動の激しい市場環境では、こうした柔軟な対応が現場で行われています。
まとめ
日々変動する青果の相場。その背景には、天候や需給、物流、さらには消費者の動きまで、さまざまな要素が関わっています。普段は見過ごしがちな価格の変化も、その仕組みを知ることで新たな視点が得られたのではないでしょうか。
近年は、輸入依存の高まりや為替の影響、消費者ニーズの多様化などにより、青果市場を取り巻く環境も大きく変わりつつあります。変化の激しい青果業界ですが、情報公開の進展により、市況や相場の動きはこれまで以上に身近に感じられるようになってきました。
本記事を通じて、青果相場のしくみや情報源への理解が深まり、日々の価格変動を読み解く一助となれば幸いです。
\📢 青果業界で働きたい方必見! /
🌱 青果業界の正社員求人が豊富な「オイシルキャリア」で、次のステップを見つけてみませんか? 転職活動は専任のアドバイザーがサポートします。あなたの経験を活かせる職場がきっと見つかるはずです。
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /