令和に入ってから続く物価高騰。2025年も野菜や果物の値上がりニュースは珍しくなく、「どうしてこんなに高いの?」と感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、スーパーマーケットの値段は市場価格、つまり市場での取引価格だけで決まるわけではありません。そこに輸送費や人件費、販売戦略などさまざまな要因が重なって変動します。
そこで、今回は、市場価格とスーパーマーケット価格の違いをわかりやすく解説し、さらに価格の動きやすい場面、安く買えるタイミング、簡単な価格チェック方法まで詳しくご紹介。
値段の背景を知れば、「高いから買わない」「安いときにまとめ買い」など、日々の買い物判断がぐっとしやすくなります。
「市場価格」とは? スーパーの値段とどうつながっているの?

スーパーで野菜や果物の値段が変わるとき、「市場価格が上がったからだ」と耳にすることがあります。
ここでいう “市場”とは、中央卸売市場や地方市場など、生産者や出荷団体が持ち込んだ青果物が取引される場所のこと。そこで決まる値段が「市場価格(卸売価格)」です。
ただし、この市場価格はあくまで “取引時点での卸売価格”。そのままスーパーの値段になるわけではありません。まずは、この市場での取引価格と店頭価格の違いを見ていきましょう。
市場での取引価格と店頭価格の違い
「市場価格(卸売価格)」とは、生産者や出荷団体が市場に持ち込んだ青果物(野菜や果物)を、卸売業者が仲卸業者や小売業者に販売する際の価格です。天候や出荷量など需給バランスの影響を強く受け、日ごとに変動します。
一方、スーパーの「店頭価格(小売価格)」は、市場価格に輸送費や人件費、店舗運営費、利益などが加わり、在庫やイベント需要、そして販売戦略によっても左右されます。
そのため、市場でキャベツが安値でも鍋フェアを仕掛けて値段を据え置いたり上げたりすることがあれば、逆に市場価格が高いときでも広告の目玉商品として赤字覚悟で安く販売するケースもあります。
このように、市場価格と店頭価格は密接に関係していますが、必ずしも同じ動きをするわけではないのです。ここを理解しておくと、「ニュースでは高騰と言っているのに、近所のスーパーは安い」という状況にも納得できるはずです。
ニュースで「高騰」と出てから家計に影響が出るまでの流れ
では、ニュースで「値上がり」と報じられた価格変動は、どのようにして私たちの家計やスーパーの値札に影響していくのでしょうか。
テレビやネットニュースで「レタスが高騰」「みかんが値下がり」と報じられても、その変化がすぐにスーパーの値札に反映されるとは限りません。実際には、次のような流れを経るのが一般的です。
- 市場価格が変動
天候不順や需要増加、出荷量の急減などで卸売価格が上がる/下がる。 - 小売業者が仕入れ価格を調整
市場からの仕入れ時に価格変動を反映。既に在庫がある場合は、値段を据え置くこともある。 - スーパーの店頭価格に反映
即日値札を変える場合もあれば、チラシや特売計画の都合で反映を遅らせることも。
このように、市場価格の動きとスーパーの価格はタイムラグがあります。
また、市場価格が高いのにスーパーが安く売る場合や、市場価格が安いのにスーパーが値上げする場合もあります。これは、特売や在庫処分、イベント需要など小売独自の戦略があるからです。
「ニュースで高騰と聞いたのに近所では安い」「市場は安値なのにスーパーでは高い」といった不思議な現象も、この関係を知っていれば理由が見えてきます。
市場価格だけじゃない! スーパーの値段が動く4つのきっかけ
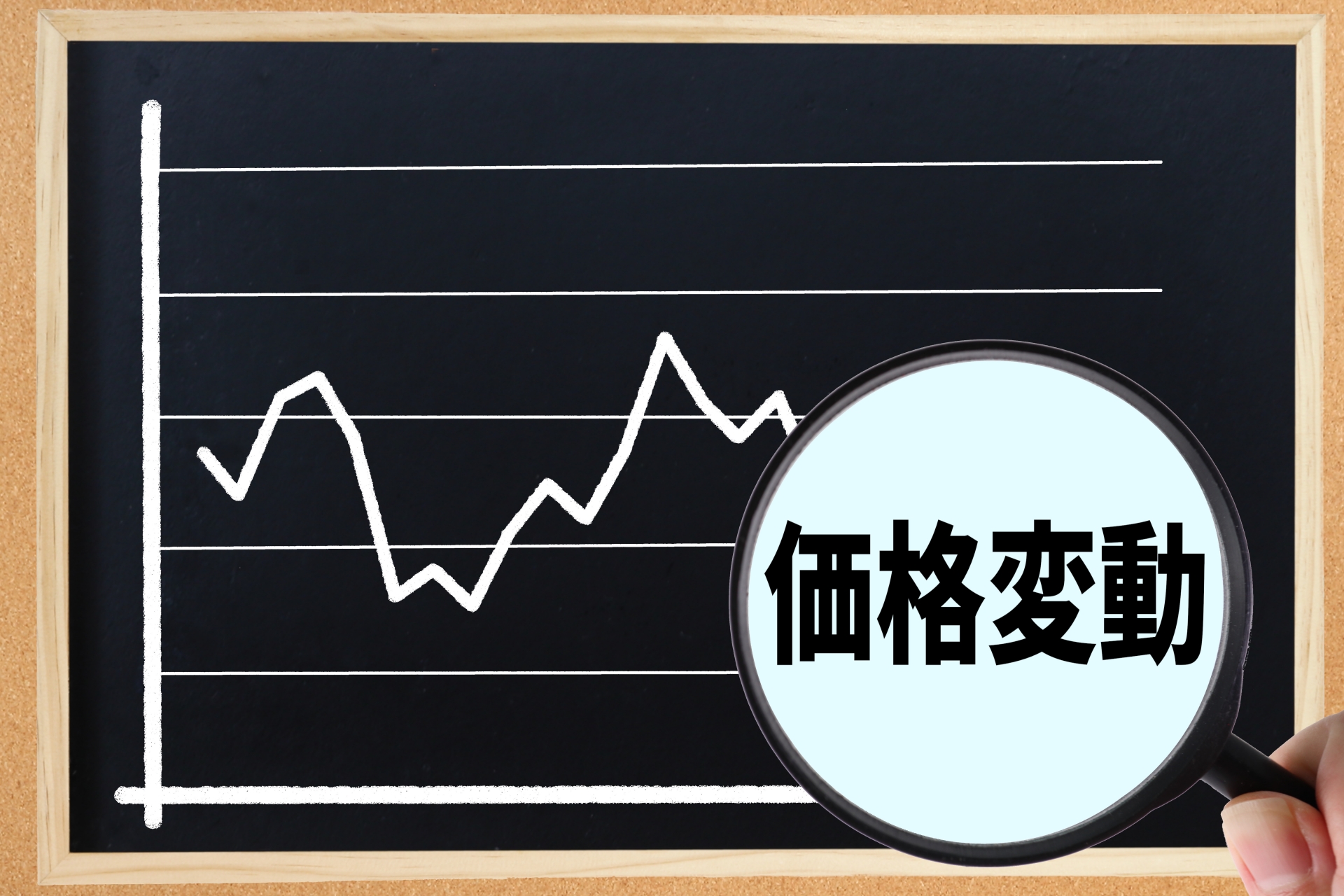
ここまで見てきたように、スーパーの値段は市場価格と必ずしも同じ動きをするわけではありません。
その背景には、市場での取引以外にもさまざまな要因が関係しているからです。ここからは、市場価格とは別にスーパーの値段を左右する4つのきっかけを見ていきましょう。
きっかけ① 天候・災害による供給変化
台風や長雨、猛暑などの天候不順は、野菜や果物の生育や収穫量に直結します。
たとえば、畑が水につかるほどの大雨や、猛暑での生育不良が起これば、出荷量は一気に減少。市場価格は上がり、その影響がスーパーの値段にも反映されやすくなります。
逆に、晴天が続いて収穫量が増えれば、市場価格は下がり、スーパーでも特売になることがあります。
夏場のきゅうりやなす、秋のさつまいもなどは、豊作の年には店頭で安く並びやすい代表例です。
📌 天候と収穫量のポイント
- 台風・長雨・猛暑などは収穫量を減らし、価格上昇の要因になる
- 晴天が続くと収穫量が増え、価格が下がりやすくなる
- 露地栽培の野菜(きゅうり・なす・レタス等)や果実(ぶどう・桃等)は影響を受けやすい
きっかけ② 旬入り・端境期など産地切り替え
野菜や果物は、季節や産地の移り変わりによって価格が動きます。
旬入りの時期は出回る量が増えて価格が下がりやすく、反対に端境期(はざかいき)と呼ばれる産地や品種・農地の切り替え時期は、供給が一時的に減って値上がりしやすくなります。
たとえば、春キャベツから夏キャベツへの切り替え時期(6月前後)は、収穫や出荷が安定せず値上がりすることがあります。
いちごも同様に、冬から春への端境期にあたる時期(4月前後)や、ハウス栽培から露地栽培への切り替え時期(5〜6月)は品質・量ともに不安定になりやすく、価格が上がる傾向でが見られます。
📌 産地切り替え時のポイント
- 旬入りは出回る量が増え、価格が下がる傾向
- 端境期は供給減で価格が上がりやすい
- キャベツやいちごなど、切り替え時は値動きが大きい
きっかけ③ イベントや連休による販売戦略
スーパーでは、需要が高まるイベントや連休に合わせて価格が動くことがあります。
たとえば、正月前の「おせち」用野菜、ひなまつり前のいちごや桃、夏休みのバーベキュー需要に合わせたとうもろこしや枝豆などは、需要増に伴って価格が上がりやすくなります。
また、需要が読めるイベント時には、仕入れ価格に関係なく値段を上げるケースもあります。これは「買ってもらえるタイミングで利益を確保する」販売戦略のひとつ。反対に、イベント終了後は在庫を減らすために特売価格になることもあります。
📌 イベント時のポイント
- イベント前は需要増で値上がりしやすい
- 需要が読めるタイミングでは仕入れ価格に関係なく高値設定も
- 終了後は在庫処分で値下がりすることも
きっかけ④ 輸入品や物流コストの変動
輸入品に頼る野菜や果物は、為替レートや海外の天候不順によって価格が変わります。
たとえば、バナナやオレンジ、アボカドなどは主要産地の天候や収穫量、さらには円安の影響で仕入れ価格が上がることがあります。
また、物流コストの上昇も価格に直結します。燃料費や人件費の高騰、輸送ルートの混乱(港の混雑や国際情勢の影響など)が発生すると、国内産・輸入品を問わず店頭価格が上がることがあります。
逆に、物流が安定して燃料価格が下がれば、価格も落ち着きやすくなります。
📌 輸入・物流のポイント
- 為替や海外の天候不順で輸入品価格は変動
- 燃料費・人件費の上昇は全品目の価格に影響
- 国際情勢や港湾の混雑も要因になる
市場価格の波を読んで節約! 旬だけじゃない “狙い目”とは?

では、一年のうち、いつどんな青果を買うのが一番お得なのでしょうか。
ポイントは、必ずしも “旬のど真ん中”だけが買い時とは限らないということ。なかには、旬だと思って買っていた時期よりも、少し前や後のほうが品質や価格のバランスが良い品目もあります。
ここからは、今日から意識できる買い物のヒントとして、スーパーでよく見かける6つの野菜・果物について、それぞれのおすすめ時期と理由を見ていきましょう。
トマトは出荷が安定する春〜初夏が狙い目!
トマトは冬から春にかけてハウス栽培が中心ですが、気温が上がる春先から初夏にかけて露地ものも加わり、出荷量が安定して価格も落ち着きやすくなります。とくに昼夜の寒暖差が大きい4〜6月は品質も良く、甘みと酸味のバランスが整う時期。
真夏は高温で実が割れやすくなったり、熟すスピードが早すぎて糖度や旨みが十分にのらないまま収穫されたりと、品質が不安定になることも少なくありません。安定した味と価格を狙うなら、春〜初夏が狙い目です。
きゅうりは価格が下がりやすい初夏〜真夏が買い時!
きゅうりは春先まではハウス栽培が中心ですが、5月頃から露地ものが出回り始め、6〜8月にかけて出荷量がピークを迎えます。この時期は安定して大量に流通するため、価格が下がりやすく、スーパーでも特売の対象になりやすい品目です。
一方で、真夏の猛暑が長く続くと変形が起こったり、傷みやすいものが増えたりすることもあります。しかし、そもそもの出荷量が多い分、品質の良いものも選びやすい時期です。
反対に、11〜2月頃は再びハウス栽培が中心となり、暖房費や管理コストの影響で価格が高めに。日照不足で香りや風味もやや落ちるため、買い時とは言いにくい時期です。
価格と鮮度のバランスを考えると、初夏〜真夏はまさに “お得に買いやすい”シーズンといえるでしょう。
キャベツは甘みが増す冬と春先がおすすめ!
キャベツは年間を通して出回りますが、とくにおすすめなのが、冬と春先。たとえば、1〜2月あたりの冬キャベツは葉がしっかりと巻き、寒さで糖度が上がって甘みが強いのが特徴です。
そして、そのあと3〜5月頃を迎える頃に収穫期を迎える春キャベツは、やわらかい葉とみずみずしさが際立ちます。生食でも美味しく、価格も比較的安定しています。
一方、梅雨時期から夏場にかけては高温多湿で品質が落ちやすく、病害虫による傷みや葉の硬さが目立つことも。また、端境期にあたる6月頃は産地切り替えで出荷量が減り、価格が上がりやすくなります。
甘みや食感、価格のバランスを考えると、冬と春先は “味も値段も狙い目”のシーズンといえるでしょう。
みかんは12月〜年末が “鉄板”、品種によっては年明けも◎
みかんは11月頃から出回りますが、酸味が抜けて甘みがのるのは12月〜年末。出荷量が多く品質も安定しやすいため、この時期は味・価格ともにバランスが良い “鉄板”の買い時です。
一方で、晩生(ばんせい)品種や、低温でじっくり貯蔵して熟成させた「蔵出しみかん」は、年明けに甘みが増すケースもあります。
ただし、皮がやや硬くなったり、品種や産地によっては風味が落ちやすいこともあるため、産地・等級表示をチェックしながら選ぶと安心です。
また、年明けは全体の出荷量が減るため、価格はやや上がりやすい傾向にあります。
品質と価格のバランスを考えると、買い時は年末まで。そのうえで、特定品種や産地ものを選べば、年明け以降も楽しめます。
ぶどうは出荷ピークを過ぎた9月がベストシーズン!
一般的にぶどうの主な出回り時期は7月下旬〜10月頃ですが、価格が落ち着き始めるのは出荷ピークを過ぎた9月。この頃は昼夜の寒暖差が大きくなり、糖度が上がりやすく、甘みと香りがしっかりとのった粒が多く出回ります。
なかでもシャインマスカットや巨峰などの人気品種はピーク時の高値から値が下がり、手に取りやすくなる時期です。
秋雨や台風の影響で裂果や傷みが見られる房もあるため、房の下部まで粒が詰まっているか、傷みや変色がないかをチェックするのがポイントですが、旬の後半ならではの値頃感と味わいを同時に楽しめるシーズンといえるでしょう。
いちごはひなまつり後の3月〜4月が値ごろ感◎
いちごは冬から春まで長く出回りますが、クリスマス〜年末年始といったイベント需要で価格は高めに推移。やっと価格が落ち着いて手に取りやすくなるのは、ひなまつりを過ぎた3月頃からです。
とくに、4月にかけては気温上昇とともに収穫量が増え、店頭価格も安定してきます。この時期は糖度と酸味のバランスがよく、果肉もしっかりしているため、あまおうや紅ほっぺなどの人気品種もピーク時よりお得に楽しめます。
一方、4月以降は産地によって露地栽培へ切り替わり、日差しや気温の影響で水っぽくなり、風味もやや薄くなりがち。生食で楽しみたい場合は、露地物が増える前の時期までがベストです。
🖊️ このように、それぞれの青果ごとに “買い時”を意識して選ぶことで、同じ予算でもより質の高い商品を手に入れられます。日々の食卓に、旬の魅力とお得感をうまく取り入れてみましょう。
市場価格を簡単にチェックする方法

では最後は、その “買い時”を見極めるヒントになる市場価格の動きや出荷情報を、手軽にチェックする方法を見ていきましょう。
普段の買い物ではあまり意識しないかもしれませんが、ちょっとした相場情報を押さえておくだけで、旬の味をよりお得に楽しむことができます。
一般の人でも見られる公的サイトやニュース
青果物の市場価格や入荷状況は、実は一般の消費者でも無料で確認できます。代表的なのは、各地の中央卸売市場の公式サイトや、農林水産省の統計ページです。
たとえば東京都中央卸売市場(豊洲市場)では、「日別取引情報」として品目ごとの取扱量や平均価格を一覧で掲載しており、せり(競り)や相対取引の結果も確認可能です。産地や等級別の価格も併せて見られるため、相場の背景が分かりやすくなります。
また、NHKや民間のニュースサイトでも、時期ごとに “野菜や果物の値動き”を特集することがあります。実際のせりの映像や、生産者・市場関係者のコメントも紹介されるため、数字だけでは見えない背景もつかめます。
📌 参考サイト例
青果物や水産物などの品目ごとに、1日の取扱量・平均価格・最高値・最低値を一覧表示。品種や等級、産地別の詳細も見られるほか、せりと相対の別や価格差も確認できます。
全国主要市場の月ごとの取扱量・平均価格の推移を集計した統計データを提供。多くはPDF形式で提供され、品目ごとの価格推移を一覧比較できます。長期的な価格動向や年ごとの比較に向いています。
🌐 各地方市場の公式ページ
(例:大阪市中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場など)
地域ごとの最新市況情報や入荷予定、主要品目の価格動向が掲載されます。地元産品の動きを知るのに最適です。
これらを定期的にチェックするだけでも、おおよその相場感や出回り量の変化がつかめます。
「見るだけ」で終わらせない! 活用ポイント
市場価格や入荷状況を確認したら、日常の買い物やメニュー作りにどう反映させるかがポイントです。情報を「知って終わり」にせず、買い物計画や献立調整に活かすことで、家計にも食卓にもプラスになります。
- 価格が下がっている品目はまとめ買い&作り置き
例:きゅうりが安い時期なら浅漬けやピクルスにして保存。 - 高騰している食材は代替品を検討
例:トマトが高ければ、缶詰や冷凍野菜を活用。 - 入荷量の少ない品目は鮮度を要チェック
相場高騰時は鮮度落ちが早いこともあるため、購入後は早めに消費。
実際、令和7年の相場表を振り返ると、天候不順で葉物野菜や一部の果実が高値となった時期がありました。こうした価格の動きは、日々の買い物にも直結します。
たとえば、市場価格よりも特売価格がぐっと下がっていれば、それは買い時のサイン。逆に相場が高騰しているときは、特売でもそれほど安くないケースもあります。
このように「見て→判断→行動」へつなげることで、相場情報は暮らしの中で生きてきます。
まとめ
野菜や果物の値段は、青果市場で決まる市場価格(相場表に掲載される値)と、スーパーの店頭価格が必ずしも一致するわけではありません。市場での取引価格は天候・産地の切り替え・需要の増減などさまざまな要因で変動し、それが時間差を伴って店頭に反映されます。
こうした背景を理解したうえで相場情報をチェックすると、「なぜ今高いのか」「そろそろ安くなりそうか」といった傾向がつかめます。そのうえで、価格が下がった品目をまとめ買いしたり、高騰時に代替品を選んだりすれば、同じ予算でもより賢く食材を選べます。
市場価格と日常の買い物を結びつける習慣は、家計にも食卓にもプラスに。旬の美味しさとお得感を両立させながら、賢い買い物を今日から始めてみませんか。
\ 📢 生鮮業界に興味がある方は【オイシルキャリア】! /
🌱 食や流通の知識を仕事に活かしたい方は「オイシルキャリア」のサポートを活用してみませんか? 食品業界に特化したアドバイザーがあなたの経験や興味を活かせる職場探しをサポートいたします!
\ 生鮮業界の求人8,000件以上 /







