「きつい」と言われることも少なくない生鮮業界。とくに卸売市場は、「セリ=速くて強い口調」といったイメージから、一般の人にとっては「大変そう」と捉えられることもあるようです。
しかし実際には、給与や待遇、働き方の面で魅力も多く、近年は職場環境の改善も着実に進んでいます。日々の食生活を支えるインフラとしての安定性も高いので、長く腰を据えて働きたい人にとっては転職先としてもおすすめの業界です。
今回はそんな青果の卸売市場について、働く方々の声をもとに現場の実態を深掘りしていきましょう。
仕事内容や業界の仕組みに加え、人間関係や文化、将来性まで幅広く取り上げていきますので、職場選びの参考としてもぜひご覧ください。
1. 青果の卸売市場の仕事はきつい? 市場の仕組みと現場が抱える課題とは
「セリで声を張る人」「重たい荷物を運ぶ人」── そんな印象が強い卸売市場ですが、実は多様な職種が関わり、それぞれに重要な役割を担っています。
まずは、青果の流通を支える現場のしくみと、市場で働く人たちの仕事について整理していきましょう。
卸売市場で働く「卸売会社・仲卸・バイヤー」の役割
出荷された青果は、まず卸売市場に集められ、その後さまざまな事業者の手を経て、小売店や飲食店に届けられます。市場内でその業務に携わる代表的な職種は以下です。
- 卸売会社(例:東京青果など)
全国から届いた野菜や果物をセリや相対取引で販売。ここでのやり取りで青果の価格が決定する。 - 仲卸業者
卸売会社から商品を仕入れ、飲食店や小売店ごとに仕分けて販売。専門性の高い目利きや顧客の希望に応じた加工も担当。 - 買受人(バイヤー)
市場内で直接商品を購入する登録業者。スーパーマーケットや八百屋、飲食店などの仕入れ担当者が多く、自社の販売戦略に合わせて青果を選ぶ。
このように、仕入れから配送まで一本の動線で結ばれる市場の仕事。役割は違っても “青果を良い状態で届ける”という共通の目的のもと、連携と信頼関係が安定供給を守っています。
新卒入社や若手が減少中… 卸売市場の現場は担い手不足が進行している
こうした多様な役割で市場が成り立っている一方で、実は現場では新卒入社を含む若手の入職者が年々減少しています。とくに「早朝勤務」や「体力的にきつい」といったイメージから、若年層の間では敬遠されやすい傾向が見られます。
そのようななか、現場ではベテラン社員が中心となって支えている状況が続いています。しかし、定年退職を迎える人も増えており、次世代の人材確保が重要な課題となっています。
なかでも仲卸業は、経験や判断力が求められる専門性の高い仕事であり、後継者育成が難しいとされています。実際に、家族経営の小規模な仲卸が廃業するケースも見られるなど、業界全体で担い手不足への対応が急がれています。
「きつい」と言われる理由とは? 卸売市場の仕事で感じる5つの負担

ここからは、具体的にどのような点が負担に感じられるのか、働く人たちの実際の声を5つ挙げてご紹介します。
それぞれの乗り越え方や、大変ながらも前向きな側面についてもあわせて見ていきましょう。
① 早朝勤務が中心になるため生活リズムに工夫が必要
青果の卸売市場は、「朝が早い仕事」の代表格です。セリが始まるのは多くの市場で早朝5〜6時台。実際は、その前に出荷物の荷受けや準備があるため、働く人の出勤は深夜2時頃になることもあります。
慣れるまでは大変ですが、午後には業務が終わることが多いので、日中の時間を有効活用できる点は大きな魅力。
家族との時間を取りやすかったり、趣味や休息に使える時間が確保できたりするのは、早朝勤務ならではのメリットといえます。
② 商品の運搬や季節ごとの気温差で体を使う場面が多い
卸売市場の仕事は、重量のある野菜や果物の積み下ろしや仕分けなど、身体を使う作業が日常的にあります。
加えて、市場の多くは屋内といえども外気に近い環境で、夏は暑く、冬は寒いという厳しさもあります。
「暑い、寒い」「体がきつい」といった声も聞かれますが、その一方で日々の作業で体が鍛えられたり、運動不足の解消になるといった前向きな声も少なくありません。
じっとしているより動いていたい人や、身体を動かす仕事が好きな人にとっては、むしろ自分に合っていると感じられる仕事でしょう。
③ 速く・正確にこなす作業が多く集中力が必要
青果市場では、セリや相対取引のあとに行う仕分けや積み込みなど、短時間で似たような品目を正確に振り分ける作業が多く、高い集中力が必要です。
数量ミスや取り違いがあると、納品トラブルや再配達、クレームにつながるため、いかに慎重かつスピーディに進められるかが重要になります。
しかし、慣れてくると「ミスなく動けた時の達成感がある」「チームで息の合った動きができると気持ちいい」といった前向きな声も聞かれます。
スピードと正確さの両方を意識しながら働ける環境は、成長を実感しやすい場面でもあるでしょう。
④ 仕入れや価格判断には専門知識と経験が求められる
市場での仕入れは、商品を見る目と価格の動きを読む力がものをいいます。たとえば、同じ「トマト」でも産地・品種・サイズによって価値は異なり、需要や天候によって相場も変動します。
こうした変化を見極めたうえで適正な価格で仕入れを判断するには、日々の経験や過去のデータ、市場内での情報交換などを通じて知識を積み重ねていくことが欠かせません。
一朝一夕では身につかない、まさに “職人技”ではありますが、「自分の判断が売上や利益に直結する面白さがある」「信頼されるようになるとやりがいが大きい」と語る人も多く、成長と達成感を味わいやすい仕事とも言えるでしょう。
⑤ クレーム対応や報告業務など人と関わる機会が意外と多い
市場の仕事は黙々と作業するイメージがありますが、実際には人と関わる業務も多くあります。
とくに仲卸やバイヤーは、取引先とのコミュニケーションが日常的に発生し、時には「傷みがあった」「数量が違う」といったクレームへの対応が必要になることも少なくありません。
市場の取引は長い付き合いになるケースが多いので、その場その場で事情を確認し、誠実に説明・対応することが信頼の継続につながります。
また、在庫報告や仕入れ先との連絡などを通じて、社内外との調整力が磨かれる点もこの仕事の特徴です。
コミュニケーションが活きる場面が多いことは、やりがいや成長につながるポイントでしょう。
青果の卸売市場の給料は意外と高い!“きつい”を越えた魅力とは

「体力的にきつそう」「朝が早いわりに給料が低いのでは?」このような印象を持たれがちな青果の卸売市場ですが、実際には収入面や待遇面で安心できるポイントも多くあります。
ここからは、初任給や手当の水準、働き方の柔軟さ、景気に左右されにくい安定性、さらに繁忙期の体制についても見ていきましょう。
年収350〜450万円も! 給与水準は比較的高めで安心感あり
青果の卸売市場で働く正社員の年収相場は、おおよそ300〜350万円が目安とされます。一方で、経験を積んだセリ人などでは 3〜5年で 400〜500万円に達するケースもあり、業界内では比較的高水準といえます(参考:Indeed「東京青果株式会社の給与情報」)。
大卒初任給も多くの企業で20〜25万円前後とされており、夜間・早朝勤務に伴う各種手当が加算されることも多いため、初年度から安定した収入を得やすい職場といえるでしょう。
この水準は、全国平均年収(約460万円) と比べても、都市部や責任あるポジションでは十分見劣りしないレンジです(参考:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」)。勤務時間に特徴があり体力的にはハードな一面もありますが、その分待遇面でしっかりと評価される環境といえるでしょう。
シフト制のメリット! 予定に合わせて柔軟に休みを取りやすい
青果の卸売市場では、作業のピークが早朝に集中するため、午前中で仕事を終えられる日も多いのが特徴です。
とくに仲卸や卸売の仕事は、午前5〜6時台に行われるセリに合わせたスケジュールで動くので、午後は比較的自由な時間を持ちやすい傾向にあります。
このため、自分の時間を有効に使いやすく、ワーク・ライフ・バランスの面でも魅力を感じる人が増えています。
また、定休が日曜・祝日と決まっている市場も多いため、家族と予定を合わせやすい点もメリットのひとつ。
市場カレンダーに合わせて週休2日や連休を取る体制も整ってきており、先の予定を立てやすいという声もあります。
「朝は早いけれど、午後は自由に使える」「人混みを避けて出かけられる」など、一般的なシフト勤務とはまた違った働きやすさがあるのが、卸売市場ならではの魅力といえるでしょう。
市場の繁忙期や休みについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
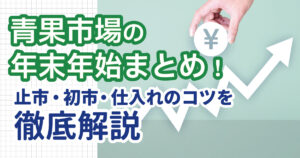
景気に左右されにくい! 生活インフラとしての安定感
青果の卸売市場は、日々の食生活を支えるインフラの一部として、景気の波に左右されにくい業態です。
野菜や果物は季節ごとに需要が安定しており、外食・中食・家庭用すべての流通に関わるため、市況全体が落ち込んだ局面でも一定の取引が保たれています。
実際、社会情勢が不安定な時期でも、業務が止まることなく続けられてきた実績があり、「仕事がなくなる不安が少ない」という声も少なくありません。
また、市場を介した取引は地域経済との結びつきも強く、生産者や買受人との長期的な関係性を軸に安定した流通が維持されています。
「食」を支えるという役割を実感しながら、腰を据えて働けるのは、青果の卸売市場ならではの大きな魅力です。
働きやすさも進化中! 繁忙期もムリなく回る現場に
青果の卸売市場では、年末年始やお盆前といった繁忙期に業務量が急増します。かつては少数精鋭で乗り切る現場も多く、体力的にも精神的にも大きな負担がかかっていました。
しかし近年は働き方改革の影響もあり、「必要なときに必要な人員を確保する」方針が浸透しつつあります。市場ごとに差はありますが、派遣スタッフの活用や分業体制の導入など、無理なく現場を回す工夫が進められています。
とくに「働きやすさ」が重視されるようになった背景には、若手の参入を促す動きや、幅広い人材を受け入れたいという業界全体の意識変化があります。まだ変化の途中ではあるものの、体制面での見直しが進んでいるのは確かです。
\ 簡単10秒で登録完了 /
独特だけど慣れれば快適! 卸売市場ならではの文化とは
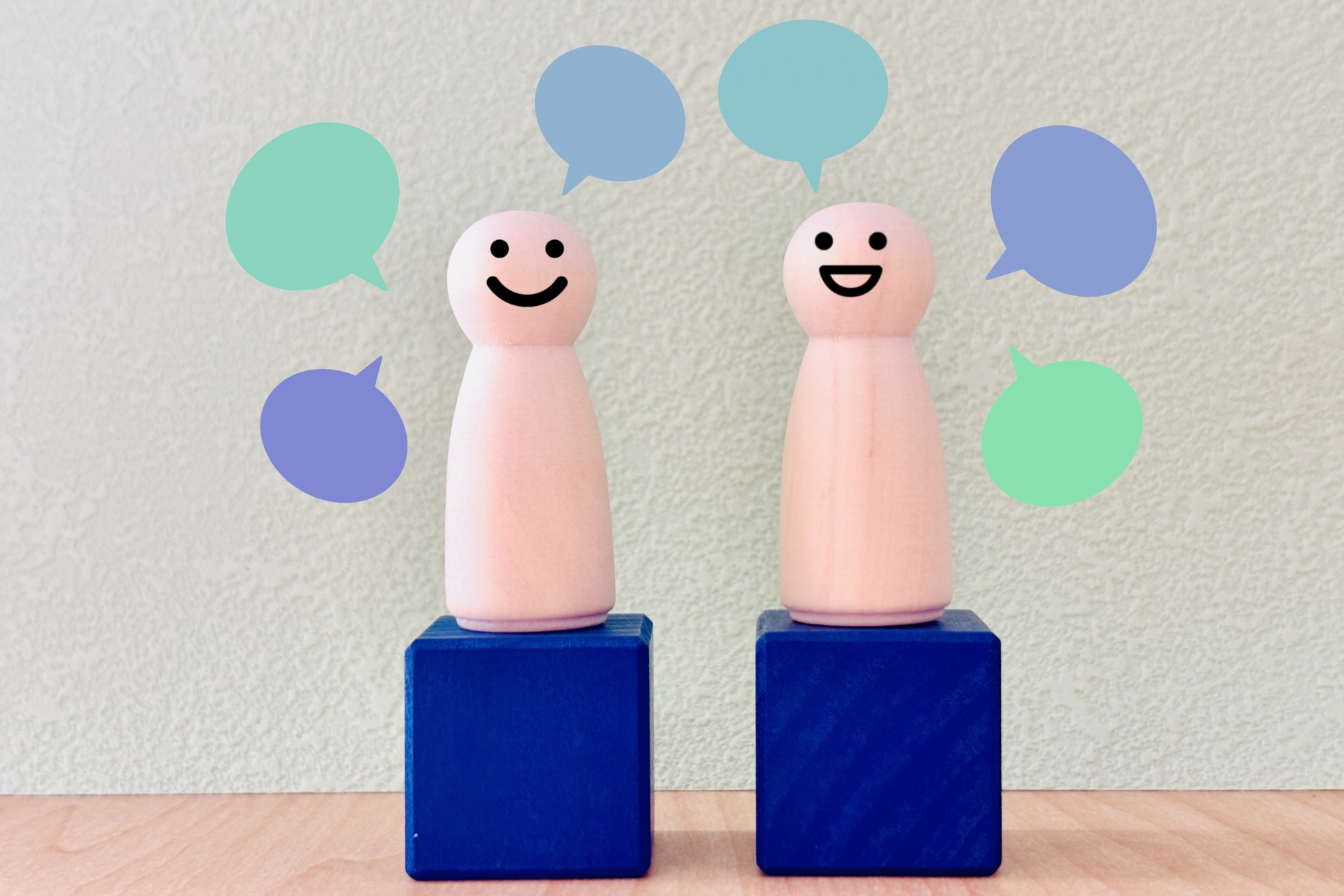
ここからは、ちょっと気になる「卸売市場ならではの文化や人間関係」に注目してみましょう。
市場の現場には、昔ながらの慣習や独自のルールが今も色濃く残っており、初めて働く人にとっては驚くこともあるかもしれません。
とはいえ、どれも仕事をスムーズに進めるための知恵や工夫が根づいたもの。慣れてしまえば居心地よく働ける職場が多いのも市場の特徴です。
ぶっきらぼうに聞こえても実は合理的? 市場の会話術
市場の現場では、日常的に独特な会話スタイルが飛び交います。
たとえば「イチゴ3(いちご1パック300円)」といった略語や、「持ってって!」「あと何ケース?」「5!」のような端的なやり取りが日常的に交わされます。
こうした一見ぶっきらぼうに聞こえる言葉づかいや短く切り上げる会話は、初めて足を踏み入れた人にとって「怖い」「冷たい」と感じられることもあるでしょう。
しかし実際には、効率性を重視した市場ならではの合理的な文化。早朝の限られた時間で大量の商品をさばく必要があるため、やり取りはできるだけ端的に、無駄のない言葉で交わされるのが基本なのです。
体育会系の雰囲気はまだある? 上下関係の距離感とは
市場で働くと、まず感じるのが「体育会系」の空気感。とくに卸売や仲卸の現場では、テキパキとした動きや声かけが重視されるため、全体的に活気があり、上下関係にもある程度の厳しさが残っています。
たとえば、先輩に対しての受け答えはハキハキと、荷物の積み下ろしなどでも自然と年功序列に近い動きが求められることがあります。
怒鳴られるような場面こそ減ってきたものの、場の空気を読みながら立ち回る力は必要とされるでしょう。
とはいえ、これは理不尽な上下関係というより、効率的に動くための “現場の型”のようなもの。慣れてくると、そのルールの中でうまく連携できるようになり、「頼られる側」へと自然に成長していく実感を得られるはずです。
信頼を得るには地道な積み重ね! 新人時代に大切なこと
市場では「誰から買うか・誰に売るか」が取引の成否に直結するため、担当者との信頼関係が非常に重要です。とくに相対取引や事前注文が中心となる今、価格や数量の優先順位は担当者の裁量(=好み)に左右されがちです。
また、青果は天候次第で需給が大きく変わるため、時には買参人と卸の立場が逆転することも少なくありません。こうした環境では、信頼される関係を築いておくことが安定した仕入れにつながるのです。
新人にとっては、日々のあいさつといったマナー面だけでなく、雑談、繁忙時の協力など、地道なやりとりが信頼につながる第一歩。
市場では自分の利益だけでなく、相手を思いやる姿勢も忘れず、持ちつ持たれつの関係を目指していくのが重要です。
青果の卸売市場は変わりつつある! 働き方や職場環境の改善が進行中
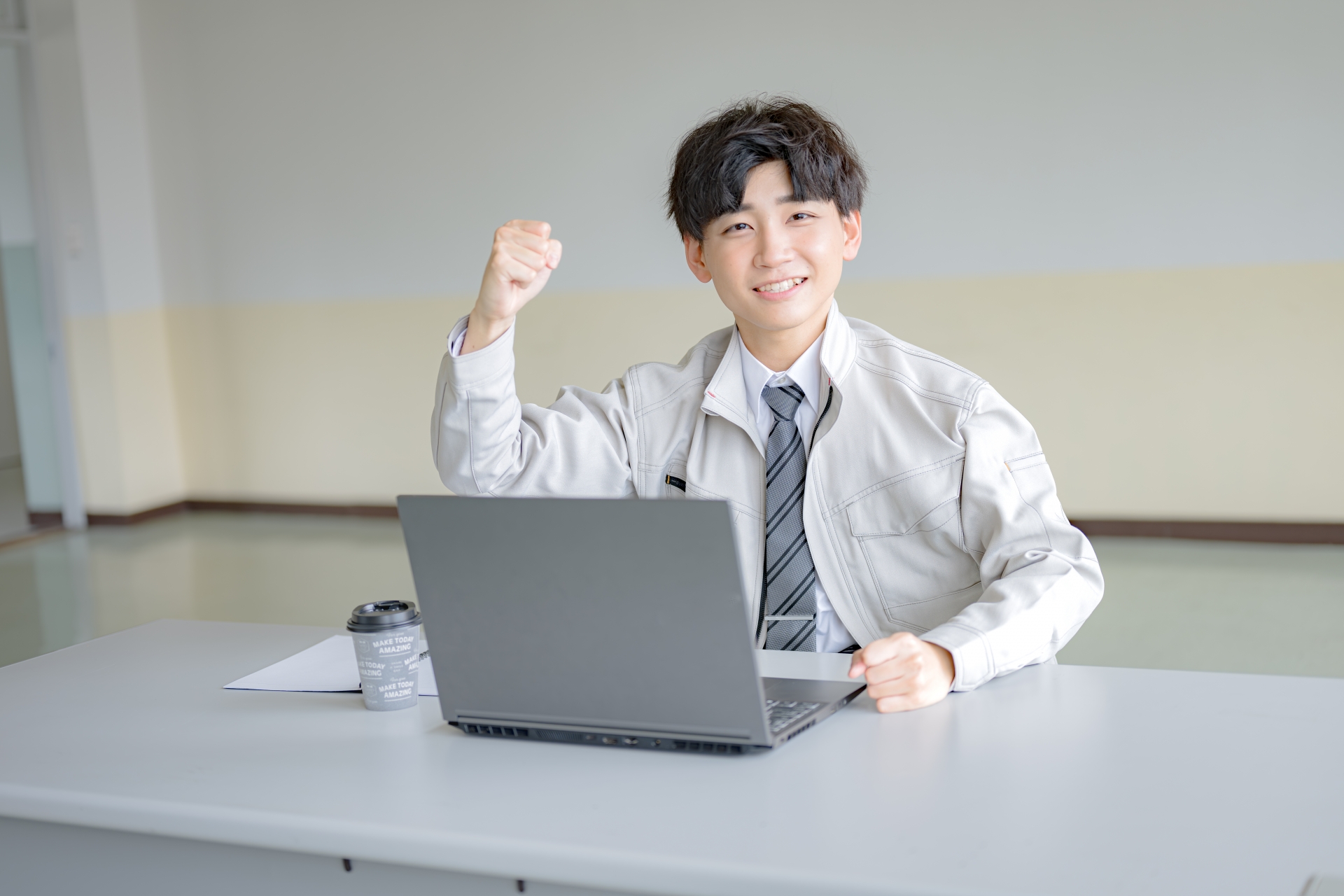
最後は、青果の卸売市場で進む働き方や職場環境の変化について見ていきましょう。
現在、卸売市場では、休暇制度の整備や評価制度の見直し、IT・機械化の導入など、持続可能な職場づくりに向けた取り組みが進んでおり、職場環境は若手をはじめとして多様な人材が働きやすい雰囲気へと着実に変わりつつあります。
指導や評価の仕組みが整い、長く働きやすい職場環境が広がっている
以前は「見て覚えろ」「背中を見て学べ」といった個人の経験や感覚に頼った指導が中心でしたが、今では新人教育のマニュアル化やOJT体制の整備が進み、誰が入っても一定のスキルが習得できるよう工夫されています。
また、評価制度も「年功序列」から「成果と意欲を反映した評価」へと移行しつつあり、若手や中途入社でも頑張り次第で昇格・昇給が望める環境が増えています。
こうした仕組みの整備は、離職防止にもつながり、長く働ける職場づくりの基盤となっています。
機械化とデジタル化が進み、業務負担が少しずつ軽減されている
青果市場ではこれまで人力に頼る作業が多くを占めていましたが、すでに多くの現場で荷物の積み下ろしにリフトやコンベアが活用され、入出荷の記録をタブレットで管理するなど、体力への配慮や業務の省力化が進んでいます。
こうした機械化の流れは、物理的な作業だけでなく取引の仕組みにも波及しており、たとえば現在は、セリの様子が一部で電子化され、モニターで情報を共有しながら取引できるようにもなりました。
これにより、ミスの防止や業務のスピードアップが図られ、とくに若手や未経験者にとっても参入しやすい環境になりつつあります。
まだすべてが自動化されているわけではありませんが、少しずつ「人の力だけに頼らない現場」への移行が進んでいます。
暗黙ルールの見直しが進み、風通しの良い職場へ!
市場独特の慣習や暗黙の了解は、長く働く人にとっては自然なものでしたが、新人や外部から来た人にとってはハードルとなることがあります。
最近ではそうした「わかりにくいルール」や「言わなくても察する文化」についても見直しが進められています。
たとえば、あいさつや報連相の重要性を明文化したり、休憩のタイミングをルール化したりと、誰にとっても働きやすい環境を整える取り組みが始まっています。
上下関係においても、指導における言葉づかいや接し方を見直す動きがあり、全体として職場の風通しは改善傾向にあります。
このように、「昔ながらの市場」にも、少しずつ“今の時代”に合った働き方が根づき始めているのです。
まとめ
今回は、青果の卸売市場をテーマに、現場の仕事から人間関係、待遇、将来の展望まで幅広く見てきました。
卸売市場の仕事は、確かに体力や集中力が求められる場面も多いですが、それ以上にやりがいや成長を実感できるフィールドでもあります。
最初に抱いていた「きつい」という印象も、少し変わってきたのではないでしょうか? この記事をきっかけに、卸売市場の大変さの裏にある魅力や、自分の力を活かせる可能性を感じていただけたなら嬉しく思います。
今後は、職場環境の整備や仕組みの見直しもさらに進んでいくと期待されています。
他業界・多職種から転職を検討している方にとっても、選択肢のひとつとして十分に検討する価値があるでしょう。
\📢 卸売市場での仕事を探すなら「オイシルキャリア」!/
🌱 オイシルキャリアでは、青果・水産・精肉など、食のプロを対象にした求人を多数掲載中。
専属のアドバイザーが、あなたの希望に合わせて転職活動をしっかりサポートします!
\ 簡単10秒で登録完了 /







